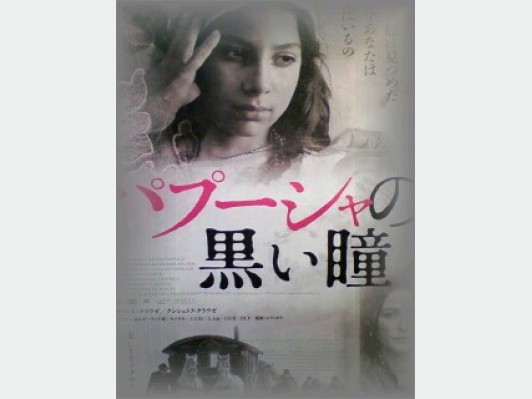"言葉を愛したがゆえに、一族の禁忌を破った女性がいた"という、
情熱的なヒロインを感じさせる映画の宣伝文句に魅かれ、
これだけは見に行かなければ、と思って、なんとか終映間際に岩波ホールに行ってきたけれど、
見ながらの感想は、予想を裏切って、なんと心弱い女性だろう、というものだった。
同じように言葉によって自分の考えを表明したために、糾弾の矢面に立ったハンナ・アーレントとはまったく違う。
ハンナは主張を変えず、時に涙を見せても自分の信念を曲げなかったけれど、
パプーシャは一族の槍玉に挙げられて簡単にくず折れてしまう。
自分の詩が掲載された本を焼いてくれ、と頼み、
それがかなわなければ、自らの手でそれまで自分が書いてきた詩を燃やし、
神経を病んで、精神科に入院してしまう。
そして退院した後も隠れるようにひっそりと暮らし、
「詩を書いたことなど一度もない」と自分の過去を打ち消すかのように語る。
まだ子供だった頃にキャンプが焼き討ちに遭えば、自分が文字を習ったせいだと思うし、
好きでもない男といっしょにならねばならなくなった時には、自分の子宮がふさがって子供ができなくなればいい、と願う。
なんという強い自己否定。自分を貶める行為。
でも、それも無理もない。
そもそも彼女が生まれて育ったジプシー社会が、
いかに森に近く、貧しいながらも自由な放浪生活を謳歌しているように見えたとしても、
それゆえに仲間たちだけで結束を固めねばならず、
よそものや、新しい考えを受けつけようとしない閉鎖的な小集団だったのだから。
パプーシャに自分のことをそのように考えるようにさせたのは、
ほかならぬ彼女を育んだそのジプシー集団、愛すべきジプシー仲間たちだ。
生まれた時から占い師の予言によってその存在を不吉なものとされ、
その言葉に縛られた大人たちによってそのような目で見られ、
そのような目で見られてきたことによって、自分という存在を忌わしきものと思い込む。
ほんとうはきっと、好奇心が強く、感受性が豊かで、頭の冴えた少女だったのだろう。
誰に言われなくても文字を覚えたいと思い、実際に誰に止められても覚えてしまったのだから。
しかしこの映画では最初から、その言葉というもの自体が、パプーシャに取って強い呪いのように働く。
占い師の予言は物語の行く末を暗示する効果的な出だしなのだけれど、
私にはその言葉のもたらすものがわかり過ぎて、ドラマチックにもなんにも見えなかった。
もちろん、だからと言ってそれがこの映画の価値を損なったわけでも、作品としてできが悪いわけでもまったくない。
誰もが評するように、モノクロームの画像は美しく、往年のジプシーたちの移動生活をその過酷さも含めて彷彿とさせてくれる。
監督のインタビューによれば一部の役者を除き、出演者たちはみなほんとうのジプシーだったというし、
白黒のコントラストのおかげか、たき火の炎からはほんとうに熱さが伝わってくるようだった。
ただ、私にはこれを、歴史に翻弄された一民族の叙事詩的物語と読むよりも、
一人の女性の悲劇的な一生を描いた哀れな物語と見るよりも、
たとえいかに周りにそう思い込まされたのであろうと、
自分を否定して生きることが、その人に取ってどれだけ不毛で、どれだけ不幸なことであるかがよくわかる映画に思えた。
むろん、パプーシャを責める気は毛頭ないのだけど。
---------------------------------------------
『パプーシャの黒い瞳』―公式サイト
http://www.moviola.jp/papusza/