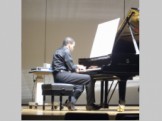そして6月30日がついにやってきた。ウィレムも神奈川県民ホールにやってきた。まずはリハーサル。調律が終わるのを待って、ピアノの前に座る。最初は、録音音源を使う曲。スピーカーの位置や音量レベルの調整をしながら弾く。ウィレム用のモニターのスピーカーが、最初は客席の方を向いて舞台の奥(ウィレムの左側)にあり、その音と舞台上部のスピーカーの音が両方聴こえる、などなど、あーでもないこーでもない、と調整して、結局、モニターのスピーカーは、ウィレムの背後に置くことになる。さらにリハーサルは続く。ステージ裏で作業をしていたら、驚くべき音が聴こえてくる。カウエルの「3つのアイルランド伝説」ではないか、し、しまった! 舞台袖のドアの覗き窓から見ると、おおおー、これがクラスター奏法! ドアをそーっとあけて、ステージの端っこで聴き入る。(写真はこの時のもの。ちょいボケててごめんなさい。この感嘆の内容は後述)。 そのあと、ウィレムはコンサートでは弾かない曲も弾いたりして、その間、オイラはずっと、おおおー!なのであった。しかし悠長に聴いてはいられない。ばたばたと準備をしながら、時々、おおおー!みたいな。
開演は19時。赤いボタンのついた黒いシャツ(ソウルでも着てたヤツだ!)に、黒いパンツ姿で、ウィレムは舞台にあらわれる。最初の曲はヘンリー・カウエルの「3つのアイルランド伝説」。うううー。これがね、すごい曲なんだわ。このブログでもこの曲のことは何度も書いているけど、生演奏ははじめて聴く。クラスター奏法というのは、前腕や肘を使って鍵盤を叩くというか押えるというか、要するに、ある範囲の鍵盤の音を全部鳴らして、音の塊みたいな響きをつくり出すわけです。でもって、隣合う音が同時に鳴っているということは、言ってみれば不協和音なわけですが、カウエルさんはこの曲では、そのぐぎゃーんという感じのポリフォニックな響きに、なんとなくノスタルジックなメロディーを重ね合わせています。その曲を演奏する姿は、かなりアクロバティック。左右の腕を駆使して、ぐぎゃーん、ぐぎゃーん、とやりながら、鍵盤を押えた側の腕の指でも、メロディーを奏でたりする。でたらめ風に見えるけれど、実は非常にコントロールが難しい、らしい。
実を言うと、ワタシも一応、ガキの頃からピアノを弾いて、全然上手にならないまま現在に至っているのですが、時々、ピアノって音がいっぱい鳴りすぎてヤダナと思うことがあります。特殊な奏法は別として、管楽器はひとつの音、弦楽器は弦の数の音、まあハープぐらいでしょうかね、いっぱい鳴るのは。でもピアノは、原理的には、鍵盤の数の音を同時に鳴らすことができる。でも人間が弾くから、10本指分の音が限界でもある。でもってワタシは、超絶技巧的な楽曲とかで、華麗にたくさんの音が鳴ったり、アンサンブルで他の楽器と一緒にピアノが鳴ると、たまーに、ちょっとヤダナと。これ見よがしなような、いっぱい鳴らしてズルイような…。という音の嗜好のあるワタクシがですね、ウィレムのこの曲の演奏を聴いていて、カウエルさんは、ピアノという楽器をとても愛した作曲家なのであろうと思ったのです。ピアノという楽器の可能性を追求して、こんな音も鳴るぞこんなこともできるぞと試しつつ、自分の内面で響く音楽をピアノの音に託していった、それがクラスター奏法であったり、彼がストリング・ピアノと呼ぶ内部奏法であったりしたのであろう、と。ワタシの勘違いかもしれませんけど。
最初にこの曲を聴いたとき、タイトルも知らないままに、おおお、波だあ!と思ったのですが、組曲の最初の曲のタイトルは"The Tides of Manaunaun"(マノノーンの潮流)、やはりアイルランドの荒れる海のイメージであるらしい。でもウィレムの演奏は、「これは海だ!」とメージを喚起させようと情感にうったえるものではなかったな(いい意味で)。ワタシは、聴いたこともない不思議な音の連なりの中にたゆたっていたのであった。
2曲目は、J・ハーヴェイ 「メシアンの墓にて」。これはCDにも収録されていている、録音音源を使う作品。どういう感じの曲かは<日記02>にも書いたけど、微妙によじれて歪んでゆく録音の音と生ピアノの音がからまりあっていく曲です。
録音部分はメシアンのピアノ曲に基づいて作曲されています。これをCDで聴く場合、どこが録音でどこが生ピアノかがわからない。実際の演奏では、それがわかる。けど、ウィレムは、スピーカーから流れる音と生ピアノの音が、区別がつかないようにしたい、と言っていた。そのへんのところが、いまひとつピンとこない。よじれる感じは好きなのですが。ゲンダイオンガクで、電気音響を否定してもしかたないのだが、どっちかっつーと、アンプラグドのほうが好きなもので。
3曲目。シュトックハウゼン「ピアノ曲第7番」(ワタクシ事になりますが、シュトックハウゼン初体験は、声のための作品のCDで、そのジャケット写真の、ニタッと笑ったようなお面の顔がなんだか恐くて、シュトックハウゼンというとその顔が浮かぶ)。これは初期の、さまざまな断片がちりばめられたような作品。音に耳を澄ます、ということを自然と促される、誠実な演奏でした。
ここで前半終わって休憩。ワタシも休憩します。後半に続く。