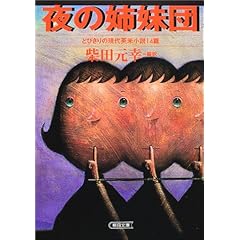文筆家・五所純子が渋谷アップリンク・ファクトリーを舞台に、ライブ書評という新しいジャンルを思索するイベント『ド評』の第六回が「娘たち」をテーマに開催された。彼女ならではの少女論、そして現代における母と娘、そして家族規範の変容を、気骨ある語り口により紐解いている。今回は、当日紹介された本の一部をあらためて紹介する。次回の『ド評』は選書のテーマを東京として11月29日(火)に行われる。
単なる悲劇としてではなく、その亀裂を産み育てていく娘たちの姿
『夜の姉妹団―とびきりの現代英米小説14篇』
著:スティーヴン・ミルハウザー 他
翻訳:柴田元幸
朝日新聞社
夏の夜に街の若い十代の娘たちが親の眼を盗んで森の先に出かけていく。何かをしているようなんだけれど、親も街の住人も彼女たちが何をしているのかさっぱり解らない。卑猥なことや猟奇的になっているんじゃないかと憶測が憶測を読んで、ただの反抗期だと見えなくなってくる。ものが隠されればそれが暗部になってどんどん危険なものになっていく、という話がすごく端正な文章で綴られていきます。娘たちをめぐる表象は諍いの場であり込み入った場なんだと思います。恐怖される対象になっているんですけれど、ふと妄想や憶測を抜いてみれば単純に彼女たちは思春期の生き物であるというところからくる情緒不安定だけが残るのかもしれない。取扱に困ったことで自分たちの娘に思えなくなり、さらに異物にしてしまう。娘たちは夜のものだということなんです。娘たちにどう対峙すべきか。夜にうごめく少女たちのイメージ。
『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』
著:ジェフリー・ユージェニデス
翻訳:佐々田雅子
早川書房
思春期の少女が死んでいく話となると真っ先に思い浮かぶのはこれで、『ヴァージン・スーサイズ』というタイトルでソフィア・コッポラによって映画化された作品です。この本のなかの少女たちにも、死にたかったわけではない、自分を消したかっただけだ、というような台詞があります。それを語るのは彼女たちではなく、五人姉妹に恋焦がれてなんでも知りたがったという「僕たち」なんです。思春期の彼女たちを見つめるには最適の複数人称かもしれません。ソフィア・コッポラ自体も大文字で書かれるようなひとりの娘ですよね。偉大な映画監督の娘である重圧。ソフィア・コッポラは『SOMEWHERE』でも強烈なファザコンを感じさせます。
『拡張するファッション』
著:林央子
ブルース・インターアクションズ
90年代から2000年代にかけてのファッションについての本で、特に焦点が当てられているのが当時言われていたガーリー・カルチャーについて振り返られていて、70年代アメリカのフェミニズムの継承とそれへの反発ということでミランダ・ジュライやソフィア・コッポラやキム・ゴードンも挙げられています。政治的なスローガンを掲げることに対する反発があり、娘のままで母親になりたかったという態度、より自然発生性を重視した世代として読みといているんです。ソフィア・コッポラの映画にどれも共通しているのが、感情表現を抑制していることで、主人公が口をきけない印象を持ってしまう。そうすると、抑圧された女性像から抜けでていないような気もするのですが、内面に耽溺しているというほど強くない。だからこそ彼女の作品にはシンパシーを覚えやすいんだと思います。
『マザーズ』
著:金原ひとみ
新潮社
最近いちばんぎょっとした小説です。これまでの自画像的なところからジャンプした小説だと思いました。それぞれの問題を抱えた3人の母親が一般化されてひとつになっていく、それから母親も娘であるんだというのが解ってくる。
なぜ人は家族を作るんでしょう。なぜ人は夫婦になろうとするんでしょう。社会的な基本だからでしょうか。それが一般的だからでしょうか。一方では、家族というのがどんどん解体されて、意味がないものだ、という論証も数十年来されてきていて、システムにすぎないものだという批判が加えられてきている。もう一方には、私たちのシステムや機構や規範が解体されていったときに、ますます私たちの生がどんどん剥き出しになって、何も守ってくれない状態になってきた。そこで、家族がどういう風に見直されていくのか。血のつながりというものが必要条件だとはまったく思わないんですけれど、セーフティネットとして見直されていく家族というもの、そういう人との結びつきを再構成するときのヒントになった箇所があったんです。それは子どもを失った夫婦間で交わされる、「あなたに似たあの子」ではなく「あの子に似たあなた」という視線の発見でした。
『マザーズ 2000‐2005未来の刻印』
写真:石内都
淡交社
石内都の母親がのこした遺品を集めた写真集です。シュミーズのレースの模様は、母が遺した皮膚のように見えます。なんで娘は母をこのように振り返るんでしょうね。母という生き物から排除された下着や口紅の写真といったものから、母の人生を解読していく。その秘められた部分から、母が女性であった、娘であったということが残されているのがこの『マザーズ』なんですよね。母が死んだ後に逆説的に『マザーズ』というタイトルがつけられて、母親の生が娘のものとして回復されていくんです。母と娘を巡る物語でありがちなのが、抑圧的であった母の生を娘がまるで相似形を描くように反復していく、精神分析的に書かれた小説はよくあるのですが、するりとこれはそこからも逃れている気がして、好きです。
『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』
著:ジョナサン・ドーゴヴニク
翻訳:竹内万里子
赤々舎
娘であることをやめるのが母になる瞬間だとしたら、強引に娘であることを辞めさせられてしまった人たちというのもいるはずです。この写真集に収められている女性たちは、1994年ルワンダで起こったツチ族とフツ族の紛争のなかで、強姦されて出産した、その母と子供です。決して望んだ妊娠でも子供でもない、その引き裂かれた関係、引き裂かれた人生が、悲惨なタッチではなく、悲惨な情感を味方にすることなく、とても直裁に撮り、それぞれのインタビューが並置されています。母になることで自分の内部に子供というかたちで亀裂を抱え込んだ娘たち。紛争で娘たちは標的にされる、そこには敵対する種族の血を絶やそうという発想があって、これもまた血の呪縛、血の神話によって娘たちは攻撃される対象として見出されていく。ここにあるのは、単なる悲劇としてではなく、その亀裂を産み育てていく娘たちの姿です。
『popteen』
角川春樹事務所
十代の剥き出しになった性の姿を垣間見るのは痛々しくも眼を惹かれますが、その最たるものがこの雑誌なんです。十代の性生活が赤裸々に綴られているとされていましたし、私も十代の頃ヤンキーの友達が貸してくれて読んだりしたんですけれど、久々に読みなおしてみて、はっきり解りました。まったく同じ文体ですし、これはライターが捏造して書いていて、これはいかんだろと思いました。投稿を実話風に改変しているのか、投稿があるなら投稿をそのまま載せればいい。奔放な性体験をどうこう言う気はないんですけど、ただセルフディフェンスは娘にとって大事なことで、それがこういう記事によって再生産されていくのだとしたら、私は同じ物書きとしてすごくやるせない気持ちになりました。
『沖縄ソウル』
著:石川真生
太田出版
十代からカメラを持ち込んで沖縄を「内側」から撮ってきた石川真生のフォトエッセイです。米軍兵士や彼らを相手に働く女性たちの姿とともに、恋愛や病の体験に触れながら自らの人生を綴っているのですが、彼女と比嘉豊光との共著である『熱き日々 in キャンプハンセン』(1982年)と比べるとなにか歴史化されてしまったという印象が残ってしまうんです。『熱き日々 in キャンプハンセン』は、噴出するような生のきらめきがわっとモノクロの写真で現れているんですが、機会があったらぜひ見てみてください。
「五所純子のド評」第七回目〈選書テーマ:東京〉
2011年11月29日(火)
渋谷アップリンク・ファクトリー
ディスク・ジョッキーならぬブック・ジョッキー。ライブで行われる書評が生み出す思考のアナザー・ディメンション『五所純子のド評』。文筆家でありながら、特定の場所に留まらずあらゆるメディアを縦断しながら活動を展開する五所純子が挑む、90分一本勝負の書評のライブ・パフォーマンス。
★今回は「東京」をテーマに書評が行われます。
19:30開場/20:00開演
出演:五所純子
料金:1,500円(1ドリンク付/予約できます)
※UPLINK会員は1,300円(1ドリンク付)
ご予約はこちらから