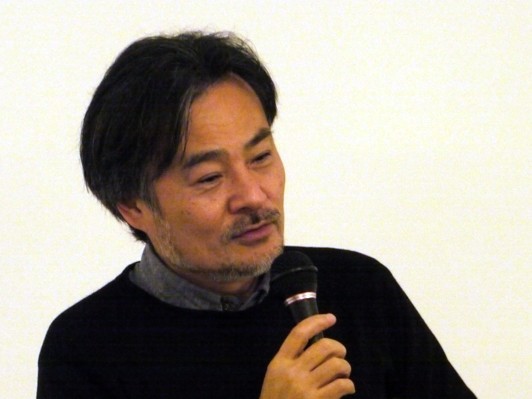黒沢清監督の映画講演集『黒沢清、21世紀の映画を語る』(boid)の刊行を記念して、6千冊の蔵書を開放する原宿のブック&カフェBibliothèque(ビブリオテック)にて特別公開講座が開催された。この日はboidの樋口泰人氏を司会に、「答える!」をテーマに黒沢監督が会場の参加者の質問に答えるという内容。黒沢作品についてのみならず、様々な映画を題材に、黒沢監督の映画論が多面的に、そしてざっくばらんに語られた。当日寄せられた質問のなかから、黒沢監督の答えをいくつか紹介する。
Bibliothèqueでは今後も映画やアートなどの書籍の刊行にともなう様々な講座やイベントを開催中だ。
具体的などこかにしないと成立しない物語は得意ではない
Q:映画には様々なかたちがあると思いますが、セルフリメイクしたいという映画はありますか?
自分がこれまで作った映画で、リメイクしたいと思うことはあまりなくて、どちらかというと思い出したくないというほうが多いのです。正直言いますと、いくつかのものはリメイクというほど美しいものではなくて、ひたすら反省なんですけれど、こうすればもうちょっと話題になったのになという、もったいないことをしたなということはあります。ネタは悪くないのになって思う映画は『ドッペルゲンガー』でしょうね。なんで受けなかったのか(笑)。ドッペルゲンガーそのものは良くあるネタなんですけれど、自分では嬉々としていたんです。あそこにもうひとりの自分がいる、自分をみてしまって怖いということで、「あっ俺がいる」、そうしたらその俺が「後は俺にまかせとけ、お前は休んでいいからおまえが悩んでいるところぜんぶ俺が引き受けるからな」ってえらいいい加減で陽気で積極的なドッペルゲンガーが現れたら、どんなに面白いだろうっていうのが発想のはじまりで。
ふたり─といっても同じ人なんですけれど─が対立しつつまた再び合体していくみたいな流れにしたんです。けれどそこがとても解りづらくて、一回分裂したふたりが再び融合して新たな自分になっているというところを思いついたのはいいけれど、やや観念的にしか伝わらなくて、もうすこしお金をかけて合体するビジュアルでみせるとかもうすこし丁寧にやっていったらよかった。
樋口:でも同じ人が合体しても、同じ人にしかならないでしょ(笑)。
ま、そうか…でもネタとして面白いでしょ。惜しい企画でしたね。
Bibliothèque地下のイベントスペースで開催された講座に登壇した黒沢清監督(左)、司会の樋口泰人氏(右)
Q:この『黒沢清、21世紀の映画を語る』のなかで、黒沢さんは漠然と世界というものに関心があると書かれていました。僕は小説家を目指しているのですが、映画を観るとき大抵は人物に注意が向いてしまうと思うのですが、僕の場合は人物よりも、ペドロ・コスタの『ヴァンダの部屋』のような、ポルトガルのスラム街で崩れるコンクリートの音であったり、ジャン=リュック・ゴダールの『自画像』のゴダールが本を開くざらついた音といったものに関心がいってしまうんです。そういったものを聞いたときにまったく違う考えが頭に浮かんでいて面白いと思うのですが、黒沢さんもそういった、全く違ったことを考えさせようと意図して脚本を書いたりするのですか?
核心に迫るご質問だった気がします。僕も映画を作っていて、自分でも悩ましいところです。この本にも書きましたが、映画はいろんなものが嫌でも映ってしまうというところから出発しています。小説を書かれるときはどういう心境かは解りませんけれど、自分が書かない限り1行も進まない。書けばそれだけ進んで、書かなかったものは、ないことになる。でも映画は監督が嫌でもカメラがあれば、そこにあるものを撮ってしまう。
ただ、その分基本的に脚本を書いているときには、極力外に向かって広がっていくよりは、書く中心にあるものを一生懸命探って書いているというのが僕のやり方です。だからあまり余計なことを脚本ではなるべく考えないようにしています。どこか解らない街、森、とか家、とか場合によっては〈ある場所〉といった場所設定があって。〈男と女〉とか非常に抽象的なところから作っていこうとします。と言っても、自分は最終的には自分で監督をして映画を撮るために書くわけですから、書いているうちにだんだん「これは東京かな」とか「これは男といっても中年男だよな」とか「役所広司?いやいや」とか(笑)、それは悩ましいです。右往左往しながら脚本を書きます。
ただそこから脚本を書き終わって、これを今からこれをもとに映画作りをはじめましょうかというあたりで、ずいぶんその脚本からはみ出ていっています。世界という言い方はほんとうに大げさなので恥ずかしいんですけれど、僕の作った物語というレベルから、もう外部のほうに、世間のほうに、外側にはみ出ていってしまいます。そこからどこまではみ出していけるのかというのが、脚本が終わったあとのひとつの具体的な映画作りになるという感じです。
会場のBibliothèqueの入口
樋口:逆に街や人を明快にイメージした脚本や自作はありますか?
基本的にはないんですけれど、予算とかいろんな状況から「東京だよね」とか、シリーズものを撮っていたりすると「たぶん浅草になるんじゃないか」と、 あまりうれしいことではないんですが、自動的になんとなく自分でも決めてしまっていることが多々あります。でも極力そういうことがないように書こうとするのが僕のやり方です。できるだけ場所を決めたくない。誰とは言いませんが、最初から場所は北九州と確信してるとか、うらやましいですね(笑)。
物語によっては、ある具体的などこかにしないと成立しないという物語があるんだろうと思うんですけれど、そういう物語から出発するのが僕は得意ではないようです。
樋口さんに聞きたいんですが、この街、しかもたいがいが自分の故郷、そういう人は多いですよね、自分のルーツを生まれ育った街を舞台にして物語を作っていく人は多いと思うんですけれど、どうしてなのかなと。
樋口:あまり世代論みたいなことは言いたくないんですけれど、最近の30代の監督達の映画を見ていて思うのは、自分の故郷で撮ってはいるんだけれど、そこが既にどこでもない場所になっているというか、自分の故郷がないから自分の故郷で撮っているように見えるんです。例えば自分のいた場所からどこかに逃れるというかたちで東京に出てきたということでもなくて、もう故郷自体が既に消滅しているような印象を受けることはあるんです。だから余計に自分が知っている場所で撮るという感じなのではないか。
あとは、ロックの文化で育った人たちとヒップホップの文化で育った人の違い、言葉のリズムや会話のなかで生み出してくるグルーヴみたいなものをベースに物語を作っていくということも大きいんじゃないかというのはときどき感じます。デヴィッド・フィンチャーの『ソーシャル・ネットワーク』を観て、あれは方言というよりも単純にパソコンの言葉でしゃべっている、文字が言葉にそのままなっていて、人物も文字のように動いているみたいな感じも受けたんです。映像と文字と言葉との境界線がよりあやふやになってきている。そういう状況のなかで自分の生まれた場所に戻っているというか、そこから始まっている、そんな印象なんですよね。
脚本を書くとき、確かに場所はなるべく決めずにやるんですけれど、どうしてもある人物を書く段になると現実が流入してきます。例えばあるひとつの科白を書いたとして、それを誰がどのようにしゃべるのかということが、嫌でも脳裏をよぎるわけです。現在僕の近くにいる人のように造形して台詞を言わせるのか、もうすこし抽象的に、普通はこういう事は言わないけれど、台詞としてはあり得るというようなところで成立させていくのか、映画の中ではどっちでもありなんだけど、この場合どっちだってものすごく悩むんです。
映画の台詞としてだけ成立している言葉って、だいたい芝居から来ているものですけれど、けっこうあるんです。典型的なのは、若い人がなにげなく脚本書いていてもそうなんですけれど、おじいさんが出てくると「わしは○○じゃ」って言う(笑)。現実にいたためしがないんですが、字面ではすごくおじいさんぽい。「僕は○○だからさ」って書かれるとおじいさんに読めない。おじいさんであるという記号を書くべきなのか、それはひとつの抽象化されたどこでもない場所として書かれるある映画の物語としておじいさんは「わしは○○じゃ」とはありえないでしょ。ということでもうすこし現実にうちの周りにいる今時の東京にいそうなおじいさん像として書いていくと、これは自然に抽象的な物語からはみ出て、現在とか東京という場所がそこに入り込んできてしまっているんですね。結局そういうものとして脚本は書きますし、実際に撮影すると、俳優にはなるべくリアルな感じでやってくださいと言ったりします。
そうするとその俳優なりの、その人が生きているある生活を引きずった台詞になっていって、でもどこか抽象的な部分を持ったり、非常に曖昧なんですけど、自動的にフィクションとリアルの中間的なものとして映画が成立していくんだと思います。

ゆったりと本を選ぶことのできるBibliothèqueの内観
日常にいてすぐ隣にある非日常としての川
Q:『黒沢清、21世紀の映画を語る』の最後のところで、水辺で映画は起こるということを書かれていたのがとても印象的で、『神田川淫乱戦争』もそうですが、ご自身の作品で川というものがどんな位置づけなのか、そしてなぜ水辺なのか教えてください。
僕のなかで川ということを言い出したのは、ふと気づいたというくらいで、昔から川にこだわりがあってというほど根拠が正しいものはないです。ここ10年くらい、この映画がすきだなというものに偶然川が出てくることが多いと思ったという、ただそれだけなんです。
僕の映画でもそうですね、『神田川淫乱戦争』も題名通りかなり川は出しました。でもそれ以上に僕の映画に頻繁に出てくるのは海でしょうね。海と川ってけっこう違っていて。日本は島国のせいでもあるんですけれど、海は行き止まり。そこから先出ていくというのはほんとうに思い切ったことで、『回路』ではほんとうに海に乗り出していくと大海原にぽつんと舟がいるという絵になる。もっと行けば外国の土地に行き当たるんですけれど、まずはこの世界から脱出するというイメージ、これ以上先に行けないというイメージで海を出すことは多いです。
僕の映画で川が出てくるのはそんなに多くはないんですけれど、『神田川淫乱戦争』では川の向こうの少年を救出に行くんだという、大げさに言うと世界を二つに割る境界線みたいなかたちで出してきたように思います。『トウキョウソナタ』では、川は出しませんでしたけれど、国境といって部屋のなかに線を引くシーンがありましたが、川に限らず塀とか金網でも、なにか線を引いて向こうとこっちが対立している、みたいなことは映画のなかでは嫌いではないです。『カリスマ』でもそういうことはあったかもしれません。川はそういう使い方がときどきあるんです。
樋口:今のお話は川の存在が作り出す空間的な役割に関するものでしたけれど、そうではなくて液体の集まりとしての川という物質的な側面もあるんじゃないかと思います。例えば『アカルイミライ』のクラゲがいる川とか、明らかに空間的な使われ方ではないと思うんです。クラゲと川が一体となった、半透明ななにか曖昧な世界がそこにぼんやりと浮かび上がってくる。
確かにそうですね。あまり自覚はしていませんでしたけれど、海の場合は、「海に行くぞ」という動きと、行き止まりだということも含めてひとつの海という独立したシーンとして物語が成立している場合が多いんです。けれど川って、川という別途のシーンではなくて、普通の街で生活しているとか、あるドラマが進行しているというなかで、歩いているといきなり水が見えてくる、それが川ということなんです。街中に突如出現する、街というシーンのなかに突然出現する水面として出てくる場合はありますね。『アカルイミライ』は確かにあちこちで狙って、なんとなく歩いていて急に川の水面が見えてくるように使っていました。何せ都会のクラゲをどう撮るかがテーマでしたし。
樋口:そういう意味で言うと、『回路』の壁に張り付いた黒いものと『アカルイミライ』の川は、同じようなかたちで考えていいのかもしれませんね。
異物ということじゃないんですけれど、日常にいてふとすぐ隣にあるちょっとした非日常としての川というのはあるのかもしれませんね。
(取材・文:駒井憲嗣)
Bibliothèque ビブリオテック
営業時間:火~土 12:00~21:00、日・祝 12:00~18:00
ご利用料金:お一人様¥500
定休日:月(祝日の場合は営業)
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-54-2 [地図を表示]
電話でのお問い合せ:03-3408-9482
公式HP
『黒沢清、21世紀の映画を語る』
著:黒沢清
発売中
ISBN:978-4990493813
税込:2,310円
版型:190 x 132ミリ
ページ:312ページ
発行:boid