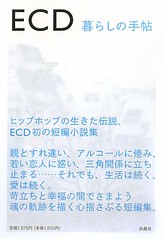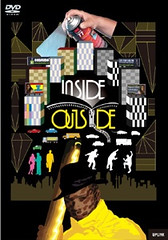ECDがニューアルバム『TEN YEARS AFTER』をリリースする。昨年リリースされたアルバム『天国よりマシなパンの耳』以降も、ジャンルを問わず続けられるライブ・パフォーマンス、そして短編小説集『暮らしの手帖』、植本一子との共著『ホームシック生活(2~3人分)』を上梓と、精力的な活動を続けている彼が発表する新作は、15年ぶりのヒップホップ・アルバムという形容もむべなるかな。リスナーとしてのめり込んでいるという昨今のヒップホップの大きなムーブメントのひとつであるサウス系からインフルエンスによるトラックメイキングは、ここ数年の極日常的な言葉の世界にさらなるアイディアと幅を与えたようだ。
ヒップホップばかり聴いている
──昨年から今年にかけてはとてもアクティブに活動されているなというのはリスナーも感じていると思うんですが、前作のインタビューの際にも「次はヒップホップな感じになる」というお話をされていて、その通りのアルバムになっていると感じました。そうすると今回のアルバムは「こういう作品にしたい」ということが頭のなかにあったのでしょうか?
今回は僕が今まで作ったアルバムのなかでも、こういう作品にしたいという意識がはっきりしていたほうですね。今までは、「そろそろ作るか」って作り始めて、なんとなくできちゃった感じなので、最初から「こういうのにしよう!」と考えて作ったのは実は今までそんなにないんですね。
――なぜ、ここ数年で再び、ECDさんの中でヒップホップが盛り上がってきたんですか?
単純に、最近また聴き手としてたくさん聴いているというのが大きくて。それで、自分でも考えて見たら〈15年ぶり〉って資料に書いてあったと思うんですけど、『HOMESICK』(1995年)を作っていた頃までなんですよ、自分が海外のヒップホップにどっぷり聴き手としてはまってたのって。その次の『BIG YOUTH』(1997年)からはもう聴き手としては離れてしまっていて。作るものも、もう少し後になると、自分の中でもはっきり(ヒップホップから)離れていきたいと言う気持ちが芽生えきていたんです。『BIG YOUTH』は作り手としてはヒップホップを作ろうという意識がそれほど薄れてはいなかったんですが、聴き手としては、たぶん1997年ぐらいにはほとんどリアルタイムのアメリカのヒップホップに興味が持てなくなっていました。そのままずっと聴いてなくて、3年ぐらい前から、またメインストリームのアメリカンヒップホップにも面白いものがあるなと思って聴き始めていて。最近は買うCDも、ダウンロードして聴いたりするにしても、新しいものとして聴いているものは全部ヒップホップばっかりです。
スチャダラパーと小沢健二による「今夜はブギーバック」のアンサーソング「DO THE BOOGIE BACK」を収録した1995年のアルバム『HOMESICK』
――それはいまアメリカのヒップホップ・シーンとして面白いものが増えているということなんでしょうか?
どうなんですかね?だとしてもそれを自分が広めたいとか思っているわけではなくて……なにしろサウスのヒップホップとか、実際(現地で)何が起こっているのか、とにかく毎日のようにフリーの音源がアップされて、それを聴く事はできるんだけどそれが現地でどんな風に受容されてるのかまるでわからない。本当に音を聴いてるだけなんです。昔はもう少し、ニューヨークならニューヨークでカルチャーとしてどうなっているのかとか産まれてくる背景とかにも興味もあったし、自分でも積極的に調べたりもしたんですが、今はまったくそういう事が解らなくて、サウスといってもサウスでいったい何がおきているのか、どんな人が聴いているのかを解らないまま、音だけ聴いて勝手に面白いなと思っていて。音だけをちょっと拝借してっていったら変ですけど、本当にそんなのばっかり聴いているので、自分の作品を作り始めても「こういう感じだよな」って、スネアのフィル入れて、みたいにしてできてしまったのが今回のアルバムなんです。
――『BIG YOUTH』以降というのは、ECDさんがいわゆる和モノであったりもっとアヴァンギャルドなものへシフトされていった時期ですね。
だから向うの新しい音のなかでも、ヒップホップが元にあってそこから発展した、97年ぐらいだったらドラムンベースだったり。2000年くらいだったらブレイクコアとか。ちょっと前だとバイレファンキやバルティモア・ブレイクスとか、そうしたヒップホップを通過した新しい音楽にはすごい興味があったんですけど、ヒップホップそのものからはどんどん離れていって。そういう聞き手としての変化を作品に反映させてきたつもりなんだけど、不器用だからそのものずばりにはならない。
佐東由梨の「ロンリー・ガール」をサンプリングした「ECDのロンリーガール」を収録の1997年作『BIG YOUTH』
――今回の『TEN YEARS AFTER』は、トラックに関してもECDさんご自身の演奏による、サンプラーを手で押すタイム感というところから、ループ感やサンプリング感みたいなものへ変化しています。
そうですね、それも含めて、ドラムがぜんぶ打ち込みなので、それもあると思うし。ライブでやっているサンプラーを手で押すタイミングでやるみたいな感じは今回一切やっていないですね。
――そうすると、トラックの作り方から焦点をヒップホップ的なものに絞って一枚のアルバムを作ってみようということだったんですね。そうした制作方法の変化は取り組んでみてどのような手応えがありましたか?
今回はわりとやろうとしたことが、思った以上にできた感じはありました。
――リスナーとして聴き込んだ部分や、頭の中にあったアイディアをうまくかたちにすることできたと?
まだ自分の中でヒップホップを聴くことが飽きていないので、今度のアルバムも向こうのものと同じに飽きずに聴けるっていうか。
日本のサウス系ラッパーに認められたいと思った
――音の構造的な変化とともに、例えば「Tony Montana」はヒップホップのクリシェとも言える映画『スカーフェイス』の主人公をテーマにしています。
必ず出てくる名前ですよね。
――今作は最近のECDさんの生活をそのままラップにする手法に加えて、そうしたいわゆる典型的なサグなヒップホップの語り口も感じられますが、それも意識されていたんですか?
意識はしないわけにはいきませんでした。でも内容は自分の身の回りのしょぼい現実でしかない。サウスを聴いていくなかで、日本でもそういうことをやっている人がいるんだなということを知って、MINTとかCHERRY BROWNを聴いて、「この感じを日本でもやっているんならいいな」と思って。この人たちに認めてもらえるようなものを作りたい(笑)、それがいちばん大きな動機かもしれないですね。今回。だから、あんまりヒップホップのメインのシーンで活躍している人たちからは別にどう思われてもいいやっていう感じは今まで同様今回もあったんですけども、最近は、ちょっとこの人たちには聴いてもらって、面白がってもらえたらいいな(笑)、そういう人が少しですけど出てきたので、こういう作品を作ってみたんです。
――日本のヒップホップのなかでも、サウスをやっている人で気になるアーティストが多いんですね。
とりあえず、今はその2人だけですね(笑)。ほかにいるのかな?……名古屋あたりにもCHERRY BROWNがツイッターで紹介してた、名前は忘れてしまったけれど、その人もmyspaceで聴いたら良かったですし。
――そのように、曲作りの段階でリスナー像を意識されていたことはこれまでもありましたか?
それはいつもあります。特に2000年代に入って、自分で作り始めてからは、ライブをやってお客さんに直接CDを手売りしたりするなかで、自分のことを支持してくれるお客さんがだいたい見えていきて、そういう人たちへ向けて作ってきたという感じはあります。そういう意味では『TEN YEARS AFTER』はちょっと違うところに向いているといえばいるんです。でも、今回の曲もライブではやっていますし。
――『TEN TEARS AFTER』には、前半のECDさんの生活をのぞき見しているような赤裸々な世界から、次第にスケールの大きないわゆるヒップホップ・アルバムとしての大作感へと続いていきますが、そうしたストーリー性については?
そこまでは考えていなくて、結果的にこういう風になったなって感じですね。でも、歌詞の内容は徹底的にこういうものにしようというのは最初からあって。前作『天国よりマシなパンの耳』で、その時期に結婚したり、子供が生まれたりしたことが、楽曲にも反映されてるんじゃないかということを期待されている人が多かったみたいで。ところが実際にはそれを全く裏切ってしまうようなアルバムだった。それで今回はこういう(個人的な内容を反映させた)形になりました。
自らのレーベルFINAL JUNKYからリリースした2009年発表の『天国よりマシなパンの耳』。「職質やめて!」「BORN TO スルー」を収録。
――サウス的なトラックメイキングの作業は、今までと違う回路を刺激される感じでしたか?
いつもそうなんですけど、サックスを始めたり、作り手として新しいことを始めると、聴き手としてもまたチャンネルが増える。全体像としてしか聴き取れていなかったものが、自分で作り始めると構造を分解できて、何が面白いのかが解ってくる。今回もアルバムを作ることでサウスが余計面白くなって、またサウスばっかり聴いてるんです(笑)。
――向こうのアーティストは意識せずにそうしたサウス的なサウンドを構築していると思うんですが、具体的な音選びの違いはどこにあるのですか?
最近やっと解ってきて、サウスの何が面白いのかというと、サウスって基本的には808がずっと鳴っていて、上物もシンセが多いんですけれど、最近の曲はサンプリングものも多くて。しかも歌もありの、ぶった切りの長いフレーズのサンプリングの上に808がチキチキ鳴っている、そこが肝なのかなと。808のハイハットが32分音符で刻まれるのが普通の曲に乗っかると、それだけですごく暴力的な効果があって。これを作っているときはそこまで気付いてはないんですけど、今一番面白いのはそこです。
――ではそこから、サンプリングすることの面白さにまた開眼したんですね。アメリカの人はその手法をどうやって発見したんでしょうか?
たぶん32分音符でやるっていうことは、ドラムンベースがやったことが一回かえってきて、またヒップホップに反映させているっていうことだと思うし。
――ECDさんも、ご自身ががいいなと思ったサウスをいちど分解して組み立ててみることで、自らのものに引き寄せることができたということですね。
そうすることで余計面白くなる。何がいいのかも解っていなかったことが、自分でやるとやっと「ここが面白かったのか」というのが解る。だから、昔みたいにサウスに関してカルチャーとして理解しようと一切していないので、そういう意味ではすごい誤解をしているかもしれないし(笑)、でもそれでいいかなって。
――15年前にヒップホップから距離を置こうと思われた時のことも教えていただきたいのですが、そうされたのは、それだけヒップホップに対して誠実でありたいという思いがあってのことなのでは?
あの頃離れたのはいろいろな理由があるんですけれども、そのなかの大きなひとつは、ちょうどビギー(ノトーリアス・B.I.G.)が撃たれたりとか、ラッパーはみんなハスラー出身でなきゃ本物じゃないとか、そういうのがついていけなくなって。まさか今さらハスリングからやり直すわけにもいかないし。じゃあ関係ないところでやるしかないなって。
――そこまで真面目に考えたのはECDさんだけじゃないですか?
いや、そんなことはないでしょう。逆にSEEDAくんとかはそういう部分まで自分にひきつけて、ほんとに自分たちでハスリングをしながらラップを作ってきたわけだし。
少しでも前向きな感じが見えると嫌だ
――今回のアルバムの最後の曲「ECDECADE」では、10年後も果たしてラップできているか、という内容のリリックがありますが、そうした歳を重ねてからもヒップホップができるか、というテーマで曲を書けるのはECDさんだけではないかと思います。
まぁどうですかね、10年後……もう50歳になっているから10年後が見えないって言っているだけで、さすがにいま30だったら、10年後余裕でやっているって言えるだろうし。それはもともと(他のラッパーより)歳が上なのでそういうことになっているだけで、それはそうたいしたことでは無いと思うんですけど。
――現在は、プライベートで赤裸々な内容の歌詞を期待されているなと感じたことはたびたびありますか?
小説やエッセイを書くことではしていたことだったんですが、ラップでは意外となかったので、今回はラップもその線で行こうと。これまでは書くものとラップとは意識的に区別していました。ラップはあくまでも音楽なので、ラップだけどあくまでも歌詞にしたいという気持ちが強くて。自分が好きな歌詞の世界、歌でしか表現できない言葉のイメージというのがあるので、それこそ阿久悠さんとか松本隆さんのような人が育んできた日本の歌の歌詞というものが。今回はそれをいったん破棄して、実はラップってこういうもんなんじゃない?っていうものをやりたかった。
もちろんラッパーの中でもリリシストと呼ばれる人はいるし、そういう側面を持っている人はいるんですけれど、でももっと向うのヒップホップを英語が解って聴くと生々しいものじゃないのかな、だったら今回みたいな形のほうが、よりラップらしいんじゃないかなって。そうした、最近の日本のハスラーラップを聴きながら、考えていたことが反映されていますね
妻であり写真家の植本一子との共著『ホームシック 生活(2~3人分)』(2009年)
──なるほど。
最近は日本語ラップでもほんとにいいなと思える作品に出会うことがあって。たとえばSCARSのSTICKYのアルバムとかSD JUNKSTAだとKYNのアルバム。それぞれのクルーのリーダー格のSEEDAやNORIKIYOはちゃんと聴いてないのに。なんか、すごいやるせない感じがよくて。
──虚勢を張りつつも、少しそこに哀愁が感じられる。
うん、にじみ出てくるものをちゃんとラップという形で表現にできる人たちがけっこういる。そこでにじみ出てくるものが、日本のほかのジャンルではあまり聴けないものなんじゃないかなと思う。だから、普通に生きる生活から外れてしまった、そのやるせない感じ。いわゆるメジャーで音楽を作って、ちゃんと食べていけている人って有能なサラリーマンと変わらない人も多いから、そういうアウトサイダーとしての感じは望めない。だから彼らには惹かれますね、ちょっと極端ですけれど、少しでも前向きな感じが見えると嫌になってしまうたちなので(笑)。
――ECDさんのそのような考えがトラックの変化とともに、ラップでのフロウなどの部分でも影響してきているのでは?
それはそうですね。これぐらいのBPMでやっている曲は最近ほとんどなかったので。ヒップホップから外れようと意識的だったというのは、90とか80という遅いBPMこそがヒップホップというイメージが、90年代前半ぐらいからずっと続いていて、それを不自由だと感じていたこともある。同じ土俵に乗りたくなかっただけかもしれないですけど。
――そうした部分で、特に今までと違う成果が出たと感じる曲は?
そういう意味では「How's My Rappin」。アルバムで最初に作った曲じゃないかな。一回やったことではあるんです。『HOMESICK』を作っているときに、RINOとかTwiggyとか〈雷〉周辺のやつらがどんどんスキルアップしているときに自分ひとり置いてかれているなと感じて、その時に自分なりに言葉の乗せ方とかいろいろ工夫した時があって。そのときの感じとちょっと似てるかな。そのあとそういう事はぜんぜんサボっていたので(笑)。今回改めてまた挑戦したという感じですね。
――「And You Don't Stop」はさんぴんキャンプをピークとした80年代後半から90年代前半にかけての日本のヒップホップの流れをECDさんの視点から捉え直したと言っていい曲ですが、こうしたテーマを盛り込もうと思われたのも、ヒップホップがテーマだったからですか?
そうですね、今までのアルバムには入れようがなかったですね。たぶん作ろうとも思わなかったし、その曲はこのアルバム制作の最後のほうでできた曲で、だいたい全体が見えてきたところで、こういう曲も入れておこうかなと。
――当時現場にいた人のみならず、体験できなかった若いリスナーに聴いて欲しいう気持ちはありますか?
いまさらどうなのかって、逆に反発をかうのではないかという気が(笑)、まぁいいかと。今さらなんだ!っていわれてもしょうがないです。そういう気持ちは特にないですね。そういう意味では今のヒップホップのシーンに戻るつもりもないので、あくまでも外にいて、こういうのも作ってみたという気持ちです。
――10曲目の「透明人間」など、今の社会での生き辛さが題材になっていると思うんですが、文章などではこれまでありましたが、リリックとしては確かに今まであまりなかったですね。
その曲がいちばん大きな変化かもしれない。前作の「職質やめて」と比較すると、別にサビが〈職質やめて〉なんだから、リリックの内容も職質についてで良かったんですが、なぜかそうならなかった。そうしたくなかった。それがどんな気持ちだか忘れちゃったんですけど(笑)。それは文章として書くかくからいいやっていう感じだったのかな……たぶん自分の中のラップ観が、前作とはがらっと変わっているんだと思うんですね、きっと。
初となる短編小説集『暮らしの手帖』(2009年)
――「Alone Again」でも、仕事に行って帰ってくるその時だけがひとりになれる時間という生活感溢れる内容が歌詞になっています。
そうですね、そういうものしか、歌詞にできないし。生き辛さというかちょっとしたストレスみたいなものは生きる上でしょうがなくまとわりついてくるので。
自分語りに関してはやり尽くした
――ライブでずっと一緒に活動されているDJのILLICIT TSUBOIさんですが、作品制作に関しても前作からまた加わっていらっしゃいますが、今回については?
前作の「BORN TO スルー」って曲でスクラッチ入れてよ、ってリクエストをしたのがきっかけで。今回は、僕のほうからこういうことを入れてというリクエストをしないまま、声ネタとかスクラッチとかを本人ががんがん入れてきて。僕が送った最初のラップとトラックがそういう風にやる気にさせちゃったみたいで(笑)。
欧米圏のストリート・アートシーンのドキュメントDVD『インサイド/アウトサイド』(2005年)。特典映像としてECDほか豪華ゲストを迎え開催されたトークやライブの模様を収録。
──では最初のECDさんのアイディアの時点でかなりヒップホップ的だったということですね。
送ったものはそうだったので。これだったらこういうのがないとな、と判断してくれたんじゃないかな。最後の「ECDECADE」にしても、1曲目の「I Can't Go For That」も早い時期から同じサンプリングネタでライブをやっていたのですが、ライブをやっていくなかでTSUBOI君が上に乗っけてきたネタをレコーディングでも乗せていたりする。そういう風にトラックができたのは初めてじゃないかな。ライブでやっていることが具体的に作品に反映してるっていうのは。
――毎回TSUBOIさんとのライブはとてもスリリングですが、ライブと曲の関係性は、ここからさらに変わってくるでしょうか?
そうですね、TSUBOI君とのライブで808を導入してみたいという気持ちもあったりするのですが、そうすると全然違うことになるので、今のところターンテーブルとサンプラーとラップの組み合わせだけでまだまだいけそうな感じはしますね。
――ヒップホップに再び立ち返って、これからの活動をどのように考えていますか?
これを作って全く白紙に戻った感じがあって。と言いながらも、もう機材はいじり始めているんですが、歌詞の内容は全く白紙ですね。これを作ることで自分をそういう状態にまで持って行きたかったのではないかとも思うし。自分語り的なことはこれでやってしまったので、このアルバムを今後に引き継げるのかというのは、自分でも解らないんです。サウスじゃなくても ドレイクとかB.o.Bみたいなポップなものよく聴いているので、それが反映されるのかされないのか。ラップのテーマも違うところに行かないとだめかなーと思ったり。
(インタビュー・文:駒井憲嗣)
【関連記事】
地引雄一×ECD『NO NEW YORK 1984-91』公開記念トークイベント「あのシーンはもう一度作ろうとしても絶対に無理なんだ」
ECD プロフィール
1960年生まれ。87年にラッパーとして活動開始、96年、イベント「さんピンCAMP」のプロデュースを経て、現在自主レーベルFINAL JUNKYを運営。2010年5月26日に最新アルバム『TEN YEARS AFTER』をリリース。著作『ECDIARY』(2004年)『失点イン・ザ・パーク』(2005年)『いるべき場所』(2007年)などを発表。
『TEN YEARS AFTER』
発売中
2,100円(税込)
FINAL JUNKY
★本文中及び上記の各作品の購入はジャケット写真をクリックしてください。
Amazonにリンクされています。