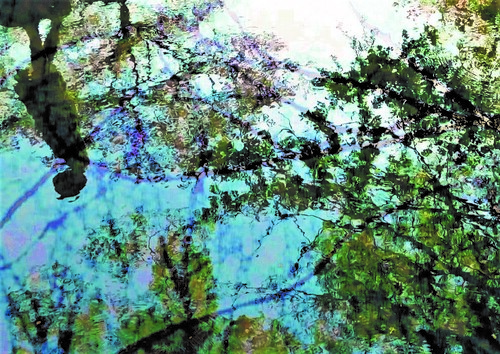三鷹SCOOL「音から作る映画」一挙上映イベントより、七里圭監督(左)、佐々木敦(左)、上妻世海(中央)
12月13日(金)から19日(木)までの1週間、アップリンク吉祥寺アップリンク吉祥寺にて、七里圭監督新作短編『Necktie』とともに、『眠り姫』や「音から作る映画」長編全作などが日替わり上映される。
今回の特集上映にあたり、批評家の佐々木敦、キュレーターで初の論考『制作へ』が話題を呼んだ上妻世海と七里監督との鼎談を公開する。採録は去る10月22日(火・祝)に三鷹SCOOLで催された「音から作る映画」一挙上映でのアフタートークより。七里作品の音と映像の謎を解き明かすトークとなった。
「あいだ」の映画
佐々木:上妻さんは今回初めて七里監督の作品を観られたと思うのですが、4本ぶっ続けで観て、いかがでしたか。
上妻:非常におもしろかったです。この映画のテーマの、実存への懐疑ということも含めて、一言で言うと〈あいだ〉の映画だと思いました。作中の人物が、役割だったり人称だったり、どこか一方に偏ることなく、〈あいだ〉に留まろうとしている。内容や手法ということだけではなく、スクリーンと観客の〈あいだ〉の問題もあります。キャラクター(役割)と役者(人物)の一致があると、観客はスクリーンに没入しやすく、観客とスクリーンの一体化が成立します。例えば大衆映画(ハリウッド映画)は、本来分離しているものをいかに癒着させるかの、技術の集積としてみることができるけど(有名なものは「sex」「violence」「loud noise」)、実際、音も映像も初めから一つのものではないですね。この「音から作る映画」シリーズは、そこをもう一度紐解きながら再統合するというような、〈あいだ〉の組み替えを目指している。それは歴史の源流に遡行することで「あったかもしれない可能性」を再構成している点で、僕としては非常に面白くて、感動しました。今まで4本一緒に上映してなかったことがむしろ不思議ですね。
七里:この企画は、京都のLumen galleryで初めてやらせてもらって、今回2回目なのですが、通しで観ると、自分でも発見がありました。『remix』公開当時、お客さんの反応があまり良くなくて。「映画でremixをやってるのになんで面白がってもらえないんだろう」と思ってたんですけど、今日はっきりとわかったのは、これやっぱり続けて観ないとわからないですね。『in progress』の後に観ると『remix』の異様さがすごく際立つ。
『サロメの娘アナザサイド(inprogress)』【12月15日上映】
『アナザサイド サロメの娘remix』【12月16日上映】
「没入」と「異化」の狭間で
七里:あいだ、と言ってくれたので関連して言うと、映画ってそもそも離人症的なものなのではないかと。録音された音、映されたイメージという、現実から切り離されたもの、バラシて繋いだものを提示してるのだから。その世界に入っていけるという状況が、異常ですよね。
上妻:実際、映画だけの話ではなく、基本的な人間のことでも言えますよね。社会的な役割でも、例えば会社員だったり、母親だったり、娘だったり、役割に完全に同一化できる人なんていないですし、多かれ少なかれ、どういう人であっても不安定さは内在的に持っている。脳と身体を見ても、感覚と運動と知覚はバラバラのモジュールでありながら、多重にフィードバックすることで不安定な仕方で統合されています。娯楽はその不安定さを解消する機能を持っています。観客である僕たちはキャラクターに同一化することで自我と自己の同一性を担保しています。言い換えたら、娯楽を精神安定剤的、安定装置のように利用している側面があります。それによって僕たちは世界を股に掛けるビジネスマンにもなれるし、地域を牛耳るマフィアにもなれるし、ロマンチックな恋愛に耽けることもできます。もちろん、それは僕たちの想像力と視点の移行性を表していて面白いですが、逆にいうと、その構造を利用して娯楽産業は成り立っている。娯楽産業におけるスクリーンとの同一化を促す技術の洗練は凄まじく、もはや人々が生き抜く上での覚せい剤になっている。使えば使うほど依存度が高くなっていく。例えば、SNSのアーキテクチャ設計にはギャンブル設計の専門家が参加していて、小さなスクリーンに僕たちを没入させ依存させるための構造を作っている。しかし、想像力と視点の移行性は現代の状況が示すような必ずしも同一化や没入を促す方向ではない可能性を孕んでいる。
七里:現代では、精神安定剤としての芸術も洗練されているけど、元々はもっと野蛮で、やばいものだったんじゃないかと。魔術や儀式だったり。そういうものが映画とかにソフティケートされて、商売にされているだけで。
佐々木:没入ということでいうと、映画だけじゃなく、演劇でもそうですよね。「没入」という方向がありながら、それに対しての異議申し立てとして、ブレヒトが「異化」と言っています。偽りのドラマの中に観客が入り込む、入り込ませながらも、これは嘘だ、ということを常に言っていく。問題は、「没入」と「異化」は、対立的にあるのではなく、両方あるんだということです。最初は映画みたいなものができたときに、観客を巻き込む没入を目指して発展していったけど、映画が、現実と呼ばれているものとどう違うのか、その違いをどのように捉え直すのか、という問題でもある。「音から作る映画」連作の劇中でも言われるように、スクリーンに映される闇は偽りの闇である。映画は現実の断片であり、影絵みたいなものの延長線上にあるんだということを、デジタルの時代にどうやって考えるかというのが、この取り組みのひとつのオーダーでもあったんですよね。
七里:デジタル時代の映画……。デジタルはレイヤーじゃないですか。レイヤーをたくさん重ねることで映画ができないか、そしてレイヤーとレイヤーのあいだのことを考えていました。
『ホッテントットエプロン-スケッチ』【12月18日上映】
音から始まる映画史?
上妻:デジタルはレイヤーである、というのは、電子音楽もそうですよね。
七里:まさに。電子音楽からのインスパイアなんです。映画のサントラ、ラジオドラマ、ミュージックコンクレートは何が違うのか。ミュージックコンクレートをサウンドトラックにした映画はありなのか、という疑問が最初。それで、電子音楽家の檜垣さんに相談したんです。
佐々木:そもそも映画史的にはおかしなことです。シネマは最初サイレントだったから、「音から作る」というのは倒錯していますよね。僕は、近年思っていることだけど、映画はたまたま最初サイレントだったけど、技術があれば音はあったに決まっている、と。音を持っていないからこその説話の技法というのも生まれたのも事実。それが正史なんだけど、最初音を持っていた、ありえたかもしれない仮想の歴史というのも言うことはできる。僕は完全にソニマージュ信者だから。映画は最初はサイレントだったけど音があったはずだ、というのを『映画としての音楽』は言っている。
『眠り姫』【12月13日、19日上映】
上妻:技術史の視点から見ると、「誰がどういう仕方で何の目的のために作ったか」と「それが人々にどう受け入れられていったか」は全く異なると言っていいと思います。例えばエジソンはラジオを遺言を吹き込む装置として作りましたし、テレビも教会の説教を聞かせるのに理想的な装置だと考えられ、インターネットは危機状態でも使える予備の通信網として構想されました。でも、実際はそうは使われなかった。歴史は常に構想や予測とは違った仕方で組み替えられていく。人類史は別の可能性を掘り起こして、それを新しい歴史にしていくというような、循環的構造を持っていて、単線的に進むというより、絶えずその地点から見える可能性、潜在性を別の形にする方向に向かって進んでいく。「音から作る映画」は、七里さんが今の2019年の地点から見える映画の可能性、潜在性を形にしたものだと思っています。だから、これは偽史でもなんでもなくて、歴史を紡いでいくことの本質だと思っています。「こうであった」という歴史に対して、「こうであったかもしれない」という歴史を重ねていくこと。この再帰的運動こそ歴史が作られる本質的運動だと思っています。「音から作る映画」の試みがこうして発表されたことで、実際に新しく系譜の種が撒かれたと言えると思います。
『あなたはわたしじゃない』【12月17日上映】
現実をモンタージュする
佐々木:「音から作る映画」シリーズは、今回上映した4本以外にも、ライブや上演など、いろんな形式の作品があります。この連作が終わって、9月の「清掃する女」の舞台映画公演があったわけですが。上演では基本的に役者さんはスクリーンの奥にいるんですよね。
七里:はい。スクリーン越しです。手前にいるパターンはすでに実演映画というものがあるので。
佐々木:そういう意味でも、例えば、エクスパンテッドシネマという言い方があるじゃないですか。拡張映画。映画を上映してるんだけど人が出てきたり、上映自体を技術的に拡張していくというものだけど、「音から作る映画」シリーズは逆だと思うわけ。なんでかっていうと、記録されたライブや上演が全部、このスクリーンのフレームの中に入っていく。拡張的なものが映画の方にどんどん食われていっちゃうんですね。それがまさに「サロメ」と、「サロメの娘」の関係になっている。つまり、『Music as film』が「サロメ」だと。そのあとが、「サロメの娘」連作になっていく。今日観て思ったのは、「サロメの娘」=映画で、「サロメ」=現実なんだということ。現実に対して、再現したり、記録したり、表象したりするものとして映画とか音響、ソニマージュみたいなものが生まれてきて、それがデジタルまでたどり着いた。この連作は、娘の方が母親を取り込もうとする話だと思いました。つまり、映画=娘の方が現実を取り込んでいって、どんどん膨張してここまできちゃったよ、なんかこんなものになっちゃったよ、と。でも、最後に「あなたはわたしじゃない、わたしはあなたじゃない」と言うのが結末。だとしたらこれで終わるしかないとうことなのかなぁと。続きはもうやりようがない。
『Musicasfilm』【12月14日上映】
『入院患者たち』【12月14日上映】
七里:以前トークで敦さんに、ここまでデジタルが現実を侵食したら、現実がずれるってことはあるかと聞いた。Youtubeとかで映像と音声がずれるみたいに。でも、それはないとおっしゃいましたよね。僕はちょっと狂ってて、あるんじゃないかと考えていて。映画とは何かと言えばモンタージュであると。ならば、現実でモンタージュができれば、映画になる。それが「清掃する女」での試みでした。で、現実をモンタージュすることはできるかもしれないという手応えを得ました。ある程度の成果は得た。
佐々木:じゃ次はあれだ、映写なし演劇だ。
七里:それ普通の演劇ですよ。
佐々木:それでどうみても映画だ、というものをやれば、それこそ倒錯的再創造ですよ。
上妻:つまり、形式を維持したまま、拡張したり転用することが一番難しいことだということですね。形式はある意味では条件であり、制限だから。「映画とは何か」を維持していながら、その形式を拡張したり裏返したりしながら、にも関わらず、「映画とは何か」を捨てきらないこと。見る人が「映画じゃない」けど「映画だよね」と思えるもの。僕は形式を捨てきらず捨て、表現なり枠組みに挑戦し続けるのが映画に限らず芸術一般に必要な態度であると思っています。
佐々木:今回は公開順に上映しましたけど、次回がもしあるなら、この連作の解決編とも言える『あなたはわたしじゃない』から始める、リバース上映というのもやってみたいですね。
2019.10.22(祝・火)「音から作る映画」一挙上映 @SCOOL〈上映後トーク〉より (採録:門谷風花 記録:日景明夫)
佐々木敦
1964年生まれ。批評家。音楽レーベルHEADZ主宰。文学、音楽、演劇、映画ほか、諸ジャンルを貫通する批評活動を行う。著書多数。最新刊は「この映画を視ているのは誰か?」(作品社)「私は小説である」(幻戯書房)。
上妻世海
1989年生まれ。おもなキュレーションに「Malformed Objects ─ 無数の異なる身体のためのブリコラージュ」(山本現代)、「時間の形式、その制作と方法 ─ 田中功起作品とテキストから考える」(青山目黒)。著作に『脱近代宣言』(水声社、落合陽一・清水高志との共著)。2018年10月、初の単著『制作へ』を刊行。
七里圭
1967年生まれ。長編最新作は『あなたはわたしじゃない』(2018)。代表作は、『眠り姫』(2007-2016)。近年は、映画製作にライブ・パフォーマンスやワーク・イン・プログレスを導入する「音から作る映画」プロジェクト(2014~)、建築家と共作した短編『DUBHOUSE』(2012)など実験的な作風で知られるが、そもそもは商業映画の助監督出身。『のんきな姉さん』(2004)、『マリッジリング』(2007)などウェルメイドな劇映画も監督。上演作に「清掃する女」(2019年9月@早稲田小劇場どらま館)、2017年には山形国際ドキュメンタリー映画祭の審査員も。
七里圭・最新短編『Necktie』+長編6作 日替わり特集
12月13日(金)~12月19日(木)アップリンク吉祥寺
【上映スケジュール】
12月13日(金)『Necktie』+『眠り姫』サラウンドリマスター版(80分)
12月14日(土)『Necktie』+『入院患者たち』(16分)+『Music as film』(54分)
12月15日(日)『Necktie』+『サロメの娘アナザサイド(inprogress)』(70分)
12月16日(月)『Necktie』+『アナザサイドサロメの娘remix』(80分)
12月17日(火)『Necktie』+『あなたはわたしじゃない』(83分)
12月18日(水)『Necktie』+『ホッテントットエプロン-スケッチ』(70分)
12月19日(木)『Necktie』+『眠り姫』サラウンドリマスター版(80分)