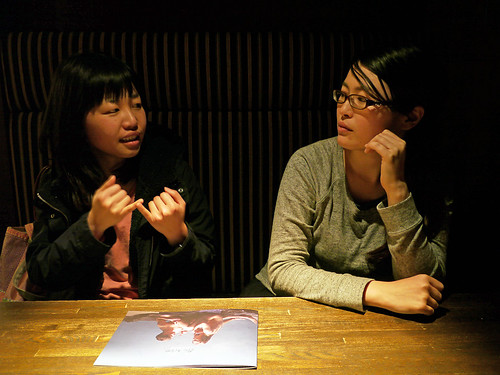映画『ザ・トライブ』より © GARMATA FILM PRODUCTION LLC, 2014 c UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, 2014
第67回カンヌ国際映画祭で批評家週間グランプリを受賞したウクライナ映画『ザ・トライブ』が4月18日(土)から公開される。今作は、聾(ろう)学校を舞台に、ひとりの少年が寄宿学校内の不良グループに入り犯罪や売春に手を染めていくようになる過程を、すべての出演者に聾唖者を起用し、全編手話により表現している。
webDICEでは、今作を観た牧原依里さんと諸星春那さんの対談を掲載。アップリンクの「配給サポート・ワークショップ」に参加しているふたりに、聾者の視点から、この作品の映画的手法や描かれる聾学校の生活、そして日本の聾者をめぐる環境について語ってもらった。手話による対談は、ふたりの友人の城戸さんと安部さんに同時に文字入力をしてもらいながら行った。
■手話という視覚的言語と長回し
──『ザ・トライブ』いかがでしたか?
牧原依里(以下、牧原):正直言うと、この映画を観て、「やられた」と思いました。何故かというと、映像制作者として、また小さい時から映画を観ていてずっと感じていたこと、この映画の監督は見事にやってのけたからです。また、こういう映画は、聾者が監督でないと難しいのではと思っていた自分がいましたが、それを聴者が実現してしまいました。この監督は類まれなる観察眼の持ち主だと思います。
諸星春那(以下、諸星):私の場合、芸術視点的というか、好みもあるかもしれないのだけど、作品としての質も含め、映像作品として完成度が高いと、観ていてそう感じたし……“字幕なし・言語は手話のみ”という事に関しては台詞と音楽に頼ってない事の証明でもあるし、そういった意味ではごまかしがきかないのだから……あえて、そういう表現したことで、すごいなーと。
牧原依里さん(右)と諸星春那さん(左)
観終わった後に『岸辺のふたり』というイギリスとオランダで制作されたアニメーション映画を思い出したんですよね。台詞がない作品で、風景を観ている感覚にも似ていたからなのか、思い出したのかもしれない。
牧原:そうですね。この映画を語る上で、ポイントが二つあるように思います。一つ目は撮り方。二つ目は、聾者像の捉え方。話が長くなってしまいますが……この映画は長回しといった非常に大きな特徴がありますね。長回しというのは、観る人が集中力を強いられる。だから、逆に見えないところも見えるようになるといった効果が生まれると思います。この監督は、実にサイレント映画的な手法をとりますね。この映画では、起こっている出来事全てをそのままストレートに映し出している。この技法は、この監督に限らず、今まで様々な監督が行ってきていますよね。
『ザ・トライブ』がそれらと何かが違うのかというと──「聾者の生の手話」をモチーフとして使ったということ。前から常々感じていたことなのですが、手話という視覚的言語は、映像に残す時、固定と長回しの技法に適している。プレスシートに記載されていた言葉──「アクション言語」という言葉を拝借するならば、手話を話す時に、アクションのように常に身体を動かしている。顔の表情も文法の一つなので、全ての身体をフル稼働しているわけです。そんな手話を映像として撮る時、映像がぶれていると、映像と手話の動きが不和協音になって、鑑賞者──特に聾者にストレスを与えやすい。
例えば、声が伴う音声言語では、カットの切り替えの連続でも、音がひとつながりになっているので、その音を基にカットを一連として観やすいわけです。しかし、身体や顔の動きが伴う手話では、カットの切り替えの連続に非常に神経を使わなければならない。前後のカットで、その人が話す手話──表情、手の動き、身体の動き、間など。それらを巧く繋ぎ合わせる必要があるわけです。手話が言語であるが故に、ちょっとしたズレが、鑑賞者──特に聾者にストレスを与えやすい。なので、手話そのものを視覚的映像として伝えたい場合、一番効果的なのは長回しになる。
今回の場合、監督が、映画は映像的なものなのだ、ということを伝えるために使った長回しが、聾者の手話の特徴と、かっちりと嵌った。見事なまでに。監督はそういう特徴を分かっていて、計算してそういう手法をとったのかなぁ?と。
映画『ザ・トライブ』より © GARMATA FILM PRODUCTION LLC, 2014 c UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, 2014
■聾学校の特徴的な閉塞感が身にしみる
諸星:そういえば、監督がキャスティングに1年かかったという事をプレスシートで読んで知ったのだけど、それに時間をかけていたことに対して、とても意味があることだなぁと。
牧原:どうしてそう思ったの?
諸星: やっぱり、聴者の役者が聾者の役をやるのはどうしても無理があると私はそう思う。演技の限度があると思うし、だから、そう言う意味では監督は自身の描く世界観に適している人、つまり、素人の聾者を探し求めていたんだなと読んで、そう思ったの。それから、『ザ・トライブ』の舞台となる聾学校の特徴というか、醸し出されているそのもの……閉塞的な雰囲気がまさにそれ。私にとってはそれがものすごーく身にしみてきたんだよね。
牧原:すごく分かりますね。聾学校を経験した人は皆共通したものを感じるのかもしれない。
諸星:聾学校の閉塞感というものは……おそらく聴者から見て、共感しにくい面もあるのかもしれないけれども、ああいう世界は未知の世界というふうに捉えているのかもしれない。
要するに、聾学校は聾者と先生だけの世界で、世間も含めて外部の世界とのつながりや関わりが薄いというものあって、ああいう特徴的な閉塞感がよく表れていると、とても実感したんだよね。
牧原:そうですね。そういう閉塞感を含めて、この映画自体が「聾者がいる!」って感じました。「聾者がいる……何が?どういうこと?」と聞かれると、上手く説明できないのだけれども……。聾学校という舞台、聾コミュニティに属している彼らが無意識に行っている行動様式、聾者の生存様式そのものをできるだけ忠実に表現しようとしている。当たり前のことなのだけれども、その当たり前のことが今までの商業映画では表現されてこなかった。だから、ウクライナ手話はわからないけど、人間としての感情を掴むことができる。何も分からないのに、手話の感情が伝わってくる。それは手話そのものを言語として、自分の血として、肉体として、骨として身に付いている聾者がありのままを演じているから。この映画は聾者なくしては成功できなかったと思う。
映画『ザ・トライブ』より © GARMATA FILM PRODUCTION LLC, 2014 c UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, 2014
──ウクライナという国自体の閉塞感のようなものも、物語と作品に影響しているのでしょうか?
牧原:そうそう、私もそう思います。
諸星:同感です。特にヨーロッパでは移民問題が多く、それについて疲弊しているような印象があるのですが、社会問題を意識している方や現状について色々と知っている方なら、観ていてそういったものの何かを感じ取っているのではないかと思います。
牧原:知人から聞いた話なのですが、とあるウクライナ聾の家族は、仕事のためにアメリカに渡り、戸籍もアメリカに変えていたのだそうです。あくまでも推測でしかないのですが、物価は上がっているのに収入が下がっていくというウクライナの状態に対してそうせざるを得ないウクライナ人も大勢いるのではないかと思います。そういった意味も含めて、ウクライナという国というものがその作品にも反映されているように見えますね。今の日本では、自国に苦しんで他の国に行く、っていうのはまず一般的ではないですから。話が違ってしまいますが、「閉鎖観から逃れる」と言ったら、今思えば、私も聾学校の閉塞感が嫌で逃れたようなもの。
諸星:私も聾学校に通っていましたので、あの閉塞感が堪らなくて、将来的に先が見えない状態が嫌で、どうやっていけばよいのかわからなかったし、とにかくそこから出なきゃ!と本能的にというか危機感を持っていました。なので、あの頃はものすごく痛感していたので、観ていて、あの頃の記憶と気持ちが再び、よみがえてきて、身にしみきった感じだったな。
牧原:逆に、今まで普通学校で育ってきて、そこでリアリティを感じられなかった聾者は、聾学校に入る事で現実感を取り戻したという人も多くいると思うね。良くも悪くも、今回の作品は監督の考え方が反映されて、たまたまそういう設定のコミュニティだったということ。
諸星:映画の中に本当の聾コミュニティがそこに描かれているから、経験者の視点から観て、色々と感じる部分もあるだろうし、共感しやすいということなのかも。
牧原:うんうん。共感できる人物……私、ぶっちゃけ、小2まで聾学校にいたんだけど、自分がボス的な存在だったのではないかと思う(苦笑)。
諸星:牧原さんを見ていればわかることだわ?!今も?(爆笑)
牧原:(笑)。もしあのままだったら……って思う時もある。聾学校を否定するわけではないのですが、自分の親が聾者なので、そういう意味で視野が狭かったし、聾学校内で援助交際みたいなものも流行っていたし、暴走族っぽい所に入っている人もいた。あくまでも、私が通っている聾学校、私が育った時代がたまたまそうだっただけなので、聾学校全てがそうじゃないことを前もって説明しておきます(笑)。今の時代、聾学校はもっと変化していると思うので。で、あのまま育っていたら、と思うと身につまされる思いになるっていうのはありますね。あの頃の私は外の世界を知らなかった。そういう意味で、登場人物に共感できるというわけじゃないけど、もしかしたら自分の一部が映画の中、映画に出ている人たちに共通している部分もあるんじゃないかと思っている。微妙な共感というのもある。
映画『ザ・トライブ』より © GARMATA FILM PRODUCTION LLC, 2014 c UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, 2014
■実は手話は世界共通ではない
諸星:手話は世界共通語ではないので、各国の言語があるのと同様に手話も各国の手話が実在しているけど、聴者は手話は世界共通しているという思い込みというか、勘違いがとても多いのだけど……。
私もウクライナ手話はわからないのだけど、観続けているうちによく出る手話があって、話の流れと行為の前後のあたりでその手話の意味が分かってくることもあったよね。
牧原:あったね。「美しい」とか「早く」とか。ウクライナ手話は日本手話と違って激しい!ウクライナの文化背景や生活環境から影響されているのではないかと思った。言語にも関わりがあるよね。
諸星:私が思うには聾者と聴者とも会話のスピードというか、その辺はそんなに変わらないというか、差はないのかもしれない。
牧原:そう?スピード的には、手話の方が早いと思うけども。
諸星:それは視覚的に見て、そう感じるからじゃない?
牧原:私、前に某大学に講演に行ったことがあるんだけど、その時に手話通訳者が、私の話すスピードについていくのに必死だった。それで、その講演を受講した人たちのアンケートの中に「手話って早いんですね」と書いてあった。手話通訳者の通訳が終わるのを待っていたぐらいだもん。
諸星:なるほど。講演での内容を音声日本語に置き換えると、やはり説明的な文章のように長くなりやすいのでは?
牧原:翻訳として、っていう意味?
諸星:そうそう。話す感覚としては聾者も聴者も関係なく同じという意味を言いたかったの。
牧原:言語として、って意味よね。
諸星:うん、それは母語だから。自然に話している感覚というか、聾者も聴者もそこまで意識しながら、常に話している訳ではないだろうし……なんだか話が壮大になってきたような?!(笑)。
牧原:そうだね(笑)。聾者像の捉え方について話を戻すと、この映画では、鑑賞者が透明人間になって、主人公や聾学校にいる聾者たちを追っていく、いわゆる聾の世界を「体験」する形になっている。手話を知らないまま大勢の聾者がいる所に行ったことがある人がこの映画を観たら、デジャヴな感覚が蘇るのではないでしょうか。それから、監督は聾者を撮る時に、聴者からの視点をできるだけ排除していることが分かります。できるだけ、聾学校という所にいる彼らの普段の姿を客観的な視点で撮ることを心がけていたことが映画から伺えます。そのために、役者に聾者を選んだのだろうし、聾者たちについていろいろリサーチしてきたのでしょう。だからこそ、聴者はこの映画を観ていて居心地が悪い感覚を覚えるかもしれないし、逆に聾者は共感を覚えやすいのではないかと私は思います。
映画『ザ・トライブ』より © GARMATA FILM PRODUCTION LLC, 2014 c UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, 2014
諸星:日本の場合、やたら、お涙頂戴的な内容や美談が多いよね?!聴者から見た聾者像が偽りそのものみたいな感じがするから、どうもね……。先入観を持った聴者が観たら、衝撃が大きいのかもしれない。
牧原:そうだね。他の映画では、「聴者の視点」から見た聾者像がある。「聾者はこうだろう、こうであるべきだ」という先入観が埋め込まれている。聴者側にフィルターがかかっている。
諸星:そういうのは色眼鏡に近いってことなのかな?
牧原:うーん、そうだね。そういった映画を観た聾者の感想は大まかに二つにわかれると思う。一つは、「おいおい」ってその映画に突っ込む、聴者からみた聾者像はこんな感じなんだ?ふーんっていう感じ。もう一つは、「聾者って頑張っているんだ、すごいと思われる存在なんだ。だから私は特別なんだ」……?ってある意味洗脳される。この二つに分かれると私は勝手に思っています(笑)。
諸星:『ザ・トライブ』の場合はどう観ている?
牧原:監督が、できるだけそういうフィルターを排除しようとしているから、そのまんまだよね?だから聾者たちの意見はいろいろ出てくるのではないかと思う。
映画『ザ・トライブ』より © GARMATA FILM PRODUCTION LLC, 2014 c UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, 2014
■本当の聾コミュニティが描かれている
諸星:それでは次に、《懐かしさ》についてのお話に入りましょうか?
牧原:そうですね。この映画観たとき、懐かしい感じがした。懐かしいというのは、自分が聾学校を経験したから。もし、聾学校を経験してない聾者が映画を観た場合、懐かしいというよりも、親近感……なんというか……親近感というよりも、なんだろう……うーん。
諸星:それは親密感なのかな?
牧原:まあ、聾学校を経験した側から言わせてもらえば聾者の行動そのものが懐かしいという意味ですね。聾学校の雰囲気も似ているし、なんというか……人間関係もああいう感じだし、スクールカーストが強い。というか、ボスが必ずいるよね。でもそれに関わりのない聾者が観た場合は……。
諸星:距離感を感じるかもしれないってこと?
牧原:距離感を感じるっていう意味ではない。今まで、中学や高校を舞台とした学園物語(聴者の映画)を観てきたが、私にとっては、別世界というか、夢物語って感じ。一応、私は普通学校に通った経験もあるけど、やっぱり情報が入らないし、周りが何を話しているのかも聞こえないから、友達の会話も分からない。だから、そういう学園物語を取り上げた映画は、自分がよく見る世界とは別の世界として楽しんでいた。逆に『ザ・トライブ』はいつも見ている風景そのままだから、今までにない感覚。リアリティというか。登場人物に感情移入という意味よりも、その場に対する共感。だから、聾学校の経験がない聾者でも『ザ・トライブ』を観ていると共感が生まれてくるんじゃないか?と感じた。
つまり、普通学校でリアリティを感じられなかった人でその学校を卒業した後に聾者コミュニティに加わっている人は、この作品を観たら、どこかで共感できる部分もあるんじゃないかと。もちろん、聾コミュニティに属していない聾者は、共感は持たないし、距離感を感じると思う。あと、日本手話を使っている聾者でも、ウクライナ手話が分かるか、分からないか、でもやはり見方が分かれると思います。ウクライナ手話が分かると、聾者の生存様式そのものよりも、物語の方に気がとられるから。ウクライナ手話が分からないと、聾者の存在そのものを改めて突きつけられるような感覚が生まれる。
諸星:そうだね。日本では聾者が受けた教育環境も様々とあるんだけど、聾学校育ち・聴者学校育ち・両方ともと、3つあるかなというふうに私はそう思っていて、それぞれ見方も変わってくると思う。
牧原:うんうん。
諸星:ウクライナの聾学校はあくまでも架空で、映画の中での話なんだけど、なんというか……リアリティがものすごくあって感じられた。
牧原:そうですね。まず、最初のバス降りた後の主人公が聴者と筆談する場面。観ていて、あぁ……という感じ。
諸星:それは「聾者のあるある!」という話ね。
牧原:そうそう。暴力も……聾者もまあまああるよね(苦笑)。暴力多いと思うよ。理由は聴者の場合は怒ると声大きくなったりするけど、聾者は手話が大きくなる。激しく早くなる。だからどうしても手が出てしまう。そうだね。うん。だから、聾者にとって、なんというか、聾者にとっては普通に怒っているだけなのに、聴者からみたら本格的にキレているという風に見られる。でも聾者同士は別に……って感じ。だから『ザ・トライブ』からもそういう似たような印象を受けるかも。
映画『ザ・トライブ』より © GARMATA FILM PRODUCTION LLC, 2014 c UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, 2014
──諸星さんは懐かしい、と感じた場面はありましたか?
諸星:いくつかあるんですけれども……まず、最初に感じたのは給食のシーンというか食堂のシーンです。そこには重複障害者が出ていたと思うんですが、それを見て、ああ、懐かしいなと。何故かというと、聾学校には聾者だけではなく、他の障害を持った聾者も何人か居るんですね。昔、私が通った聾学校には居ましたので。あと、教室のシーンもそうでした。雰囲気もそうなんですが、机の並べ方が教壇を囲んでいるというのも、聾学校の特徴ともいえるし、それで懐かしいなと思いました。
──主人公の男の子・セルゲイは、途中から思いを寄せる女の子・アナへの執着が増して、ラストの行動に至りますが、彼の心理状態をどう解釈しましたか?
諸星:うーん、彼の心理状態に関しては共感することは正直に言ってあんまりなかったですね。登場人物の中で共感する人物は特に居なかったけれども、長回しが特徴的なので、観ている間はずーっと俯瞰的に映像を見ている感覚で、観察に近い感じでしたので、そのせいか感情移入することが薄かったのかもしれないです。
牧原:私も彼に共感はできないですね。ただ……主人公が置かれた状況や環境は分からないのですが、アナに執着したセルゲイは、それしか生き甲斐がなかったのではないかと思う。つまり主人公は視野が狭い。色々なことを知らない。だからこういう状況になった時に色々な可能性を考えることができない。耳が聞こえないが故に情報も入らないから、女の子がここから居なくなったら、自分はこれからどうしていけば良いんだ?という。そういう短絡的な考え方をせざるをおえない状況下に置かれたのかなと私は解釈した。実際に日本もそういうケースが多々ある。そういう事例を聞くと、もう少し視野が広ければ、その人を理解してくれる人がいれば、そういうことは起こらなかったのではと感じることもある。もちろん、聾者に関わらず、聴者にも言えることですけど。そういった環境や実情を、作品を通して表現しているように思いました。
映画『ザ・トライブ』より © GARMATA FILM PRODUCTION LLC, 2014 c UKRAINIAN STATE FILM AGENCY, 2014
──最後に、おふたりの今日の言葉を借りると「聴者のフィルターがかっていない映画」を今後日本で作ることができるでしょうか?
諸星:……とても良い質問なんですが、答えようがない。うーん、強いて言うとしたら監督が聾者で、なおかつ聾者のアイデンティーを持つ人だったら作れるのかもしれない……?と思っちゃうんだけど……。
牧原:いやーアイデンティティに関わらず、それだけではもちろん無理でしょう。表現方法に関しては、聞こえる・聞こえないに限らず、客観的な眼を持てる人がこのような映画を作れるのだと思う。ただ、「聴者のフィルターがかかっていない映画を観たい」と思う人たちがいても、まずは表現者がその映画を作れる環境下にあるのかどうか、ですよ。社会福祉の視点で障害者を見ている日本人たちもたくさんいますし。それから、そのような映画を作れる日本人は、あちこちにいると思いますが、それを作れたとしても、果たして国内で受け入れられるかどうか?です。今の日本はそのような可能性を潰している。
諸星:あー、それは牧原さんが大好きなキム・ギドク監督の作品みたいなものだよね。
牧原:そうそう。韓国はまだ受け入れられている方かも。北野武監督も大好きで、『あの夏、一番静かな海。』も聴者が聾者を演じているのですが、あれはこの『ザ・トライブ』と同じように、映画は映像的なものだということを示すために作られた。なので、私はものすごく好きなんですが、あの映画を受け入れられない聾者もたくさんいるんですよね。聾者のリアリティがそこにないから(笑)。ただ、聾者の深川勝三監督(故)の作品のように、聾者たちが聾者の人生を演じ、それを聾者たちが撮った、そんな作品が、聾者聴者関係なく受け入れられた例もある。最近ではNHKで岩井俊二監督司会の、映画制作のついての番組「岩井俊二のMOVIEラボ」がオンエアされたり、映画業界の中でインディペンデントな力を求める流れが出ているようなので、表現者が諦めない限り、表現を追求していく限り、日本にもそのような映画を支援していく流れがこれから盛り上がってくるんではないかと思います。それを期待するしかないです。
(2015年3月5日、渋谷アップリンクにて 構成:駒井憲嗣)
牧原依里 (まきはらえり)プロフィール
2014年ニューシネマワークショップにて映画クリエイターコースを受講、会社勤めをしながら映像制作に勤しむ。現在、聾者の音楽をテーマにした映像詩を制作中。
諸星春那 (もろほし はるな)プロフィール
2015年 アート・アニメーションのちいさな学校 修了予定。コマ撮り制作を通して、アニメーションは命を与えて動かす事に魅力を感じて、今後も制作活動をコツコツと続ける。
映画『ザ・トライブ』
4月18日(土)よりユーロスペース、新宿シネマカリテほかにて公開 全国順次ロードショー
聾者の寄宿学校に入学したセルゲイ。そこでは犯罪や売春などを行う悪の組織=族(トライブ)によるヒエラルキーが形成されており、入学早々彼らの洗礼を受ける。何回かの犯罪に関わりながら、組織の中で徐々に頭角を現していったセルゲイは、リーダーの愛人で、イタリア行きのために売春でお金を貯めているアナを好きになってしまう。アナと関係を持つうちにアナを自分だけのものにしたくなったセルゲイは、組織のタブーを破り、押さえきれない激しい感情の波に流されていく……。
監督・脚本:ミロスラヴ・スラボシュビツキー
出演:グレゴリー・フェセンコ、ヤナ・ノヴィコヴァ
製作・撮影・編集:ヴァレンチヌ・ヴァシャノヴィチ
英語題:The Tribe
2014年/ウクライナ/132分/HD/カラー/1:2.39/字幕なし・手話のみ
配給:彩プロ、ミモザフィルムズ
公式サイト:http:/www.thetribe.jp
公式Facebook:https://www.facebook.com/thetribejp
公式Twitter:https://twitter.com/thetribejp