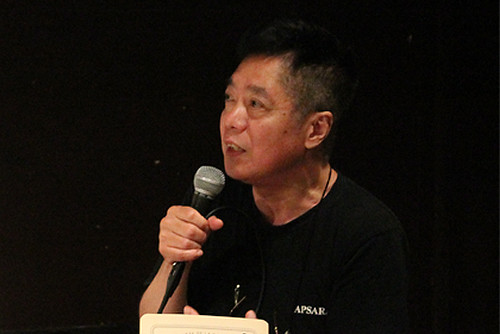渋谷アップリンク・ファクトリーにて、左より安藤紘平、浅井隆、森崎偏陸
アレハンドロ・ホドロフスキー監督作品『リアリティのダンス』の公開を記念し、寺山修司主宰の演劇グループ・天井桟敷の元劇団員、安藤紘平、森崎偏陸、浅井隆をゲストとして迎え、渋谷アップリンクでトークショーが開催された。かねてから寺山修司の映像作品との共通性を指摘されるホドロフスキーの作品。天井桟敷の団員として寺山作品に携わった3人だけが知る、寺山修司の世界とホドロフスキーの世界のシンクロニシティが語られた。
『エル・トポ』を観ないと「前衛」なんて言えなかった
浅井隆(以下、浅井):ホドロフスキーは今年85歳。寺山さんが生きていたら今年79歳なので、ホドロフスキーより若い。映画を観た人の中にはツイッターなどで「ホドロフスキーの『リアリティのダンス』は寺山的だ」という人もいますが、年齢でいえば実は寺山さんがホドロフスキー的だったということができるのではないかなと思うんです。僕が天井桟敷に入団したのが74年。『エル・トポ』が日本で公開されたのは70年。僕は当時大阪の高校生だったので『エル・トポ』の日本公開は何の意識も自分の中に刷り込まれていないのですが、ふたりは東京で『エル・トポ』の公開時にどこでご覧になりましたか。
安藤紘平(以下、安藤):普通の映画館で観ましたよ。あれを観ないと「前衛」なんて言えなかった。街を歩けなかったですよね。
森崎偏陸(以下、森崎):アングラを自称する人は『エル・トポ』を観なければだめだった。
浅井:では当然寺山さんも日本公開時に『エル・トポ』を観たわけですね。
森崎:ホドロフスキーと戯曲家のフェルナンド・アラバールは友人ですが、アラバールの脚本・監督作『死よ、万歳』のスチールと『エル・トポ』のスチールの構図が全く一緒なんです。馬に乗っている主人公がいて、『死よ、万歳』は男が下にいるんだけれど、『エル・トポ』はお母さんの写真がある。アラバールは『死よ、万歳』で初めて映画を撮りました。『エル・トポ』とどっちが先に撮られているか分かりませんが、とにかく寺山さんは両方好きでしたね。
映画『エル・トポ』より
浅井:では当然、天井桟敷の劇団員も観ていたわけですよね。
森崎:観ていましたね。当時印象に残っていたのが、手のある人が上半身、手のない足のある人が下半身を演っているのがすごいショックだった。
安藤:寺山さんの演劇で身体性は必ずテーマとしてありました。だけどなかなかそういうところまで……。
森崎:役者としてとしてなかなかそういう人を使えないじゃないですか。だからショッキングでしたし、ホドロフスキーに対してすごく嫉妬していましたね。
安藤紘平
現実と非現実が混在する語り口
安藤:ホドロフスキーのマジック・リアリズムについて話しましょうか。ラテンアメリカ以外にも、ロシアや日本、インドネシア、マレーシアといったアジアでもみられる表現ですが、もともとマジック・リアリズムの発祥はドイツなんですね。ドイツの写真家フランツ・ローが名づけたのです。現実にあるものと現実にないものを融合させて表現する芸術形式で、フリーダ・カーロのような絵画や、文学でいうとガルシア・マルケスの作品が代表的です。彼の『百年の孤独』から、ホドロフスキーや寺山さんにつながると思うのです。
『リアリティのダンス』や寺山さんの作品にも共通するのは、歳をとった自分が少年時代の自分と出会うということが物語のなかで自然にできています。幽霊やファンタジーではないのです。そういう形態ではやはり青森という土地の持つ神話や伝説とも繋がってくる。シュルレアリスムになると、フロイトの精神分析といったものが由来になりますが、そうではなく、神話や伝説や土着的なもののなかで現実と非現実が混合しても何の不思議もないという語り口が日本にもあって、そしてラテンアメリカにもあった。だから、そこで寺山さんとホドロフスキーの間に共通点があるのではないでしょうか。
森崎:『田園に死す』(1974年)と『リアリティのダンス』は自分に出会うというところで似ていますね。『田園に死す』では昔の自分に「お前の過去は変えられない」と語りかけます。寺山さんは冷たいけれども、ホドロフスキーは「お前の過去はそのままずっと受け取っていいんだよ」という言い方をしているから、また違うのだけれども。
森崎偏陸
安藤:『リアリティのダンス』では「飛んじゃダメだよ」と少年時代の自分を後ろから抱きしめます。あのシーンは『タイタニック』を超えるよね(笑)それから、『田園に死す』の最後のシーンは『ホーリー・マウンテン』の最後のシーンと似ていますよね
浅井:寺山さんは『ホーリー・マウンテン』を観た後に『田園に死す』のエンディングを考えたと思いますか?
森崎:『ホーリー・マウンテン』は「これは映画なんだ」とズームバックして終わるんですが、『田園に死す』は、これが映画なのか、それとも現実なのかというところを曖昧にしている。寺山さんはもう少し嘘のまま引きずっている、とは思います。
映画『ホーリー・マウンテン』より
浅井:寺山さんの『書を捨てよ、町へ出よう』では最後のクレジットでスタッフ、キャストの顔をずっと映していく。あれは映画の中の顔なのかそれともオフの顔なのか分からない。映画の途中で「客電をつけてください!」というセリフに合わせて本当に劇場の客電をつけたり、というようなこともやっているから、虚実入り乱れさせるという表現の方法論は寺山さんにあるものでしたね。
安藤:先ほどもあった青森的なものとの繋がりがあると思う。そういう意味でいうと、マザー・コンプレックスなんて真似もへったくれもないわけです。たとえば「母殺し」というテーマ。『サンタ・サングレ』では母親殺しをするんですよね。母親に束縛されて自分の手が母親の手になっている形になっているのに自分を解放するために自分自身というか母親を殺すわけです。それって寺山さんですよね。
浅井:なぜ寺山さんは実の母親をずっと近くに置いていたのでしょうか。
森崎:底知れずマザコンだったのでしょうね。青森県三沢市の小学校時代、いつも怒られているのに、お母さんが帰ってくるのを柱時計の下でずっと待ち続けていた。「お母さん、僕をもう一度妊娠してください」と『草迷宮』のセリフにあるように、自分を守ってくれる人はこの人しかいないと思い込んでいたのだと思います。
安藤:母親も「自分しか修ちゃんを守れる人はいない」と言っていましたからね。
森崎:お互いの絆は憎み合いながらも途切れることはなく、がっしりとあった。でも、『書を捨てよ、町へ出よう』で家出しなさいと薦められて、実際に家出して天井桟敷に入団したのに、しばらくして寺山さんに「おふくろに会いにいこうか」と言われたときは、え、何!?寺山さんは母親と仲良くしてるわけ?と、凄い騙された感じがして(笑)。晩年、寺山さんがお母さんが別の部屋に住んでいた渋谷の松風荘に帰らず、三田の人力飛行機舎で仕事してる時、お母さんが作ってくれた、しじみ汁を、毎日僕が、寺山さんに届けてました。それから、谷川俊太郎さんから聞いたのですが、寺山さんが亡くなったあと、アメリカの人が寺山さんの詩や短歌、戯曲を翻訳して出したいという依頼を、お母さんは「修ちゃんの言葉は日本語だから活きるんです。翻訳されては困ります」と断ったそうです。
浅井:寺山さんとしては、『田園に死す』を作らないと次に行けなかったわけですね。
安藤:せめて映画の中では殺してしまえ、と。
浅井:そこがホドロフスキーと違う。ホドロフスキーは父親を憎んでいたけれども、映画の中で良き父親、あるいは理解できる父親として再生させています。
安藤:ホドロフスキーはファーザー・コンプレックスではないんです。つまり、父親の弱さも指摘しています。ところが母親に対してはもう神でしょう。劇中で父性、父権の崩壊はありましたが、母は神でした。
森崎:寺山さんと同じように、母親は絶対的な強さを持っているんだと思います。
映画『リアリティのダンス』より
『リアリティのダンス』は自分の過去に対して優しい
浅井:では、寺山修司とホドロフスキーの決定的に違うところはなんだと思いますか。
安藤:違うところはたくさんあると思います。寺山さんはあんなに優しくない。『リアリティのダンス』は自分の過去に対して本当に優しいと思って。寺山さんも自分が好きなんですが、ホドロフスキーは自分に対して熱愛ですよね。
記憶の中にずっと探すけれども自分が見つからない、というようなセリフがありますが、寺山さんも「死の日より逆さに時を刻みつつついに今には至らぬ時計」と詠っているんです。結局、死んだところからずっと時を戻していって自分の記憶の中をたどっていくのに、自分に出会えないという意味です。そういうことでは寺山さんとホドロフスキーは「真似している」「真似していない」ではないと思います。やはり二人は違うんです。違う中で同じ言葉や感覚が出てきているのは、やはり何かある種のラテンアメリカにあるものと恐山にあるものが近いのでは。むしろ神の仕業ではないでしょうか。
映画『リアリティのダンス』より
森崎:彼らの記憶の中にある遺伝子にどこか同じものがあるのかも知れません。アラバールについてなど、いろいろなところで一緒になっていると思います。
浅井:二人は寺山さんのフィルターを通さず『リアリティのダンス』を観て、どこが一番印象深いですか。
安藤:僕はこの数年で最高の映画です。近来これだけの力があり、自分の過去を含めて思い出させてくれる映画で、しかも驚かせてくれる映画はなかった。海に石を投げると魚が大量に打ち上げられる、あのシーンだけでこの映画をみて良かったと思いました。
森崎:『エル・トポ』と『ホーリー・マウンテン』の時代は若さゆえの憎しみがあって、まだ冷たいんです。その時点では寺山さんに似ていると思います。まだ怒りの方が先にあった。ところが84歳になると、怒りを他のメタファーに変えてしまう。それがすごい。しかも他のメタファーに変えながら力が全く衰えない。これはすごいと思った。
浅井:この作品の前にホドロフスキーは、三男のテオを亡くしましたが、原因はオーヴァードーズだったとホドロフスキー本人は言っていました。次の作品『ホアン・ソロ』はテオを主役にしようとしたけど亡くなってしまったのです。その辺りからタロットを研究して、今回の来日の際の取材でも『リアリティのダンス』は「自分を癒すために撮ったと」言っています。サイコマジックを発明し、ヒーリングする術を自分にかけたというのが本作であると。ですから『リアリティのダンス』はホドロフスキー自身の為の映画だと思いますが、その作品が多くの人を感動させる。メキシコでも満席で客席は涙を流す人が大勢いたと聞いています。ホドロフスキー作品で泣くなんて、今まで考えられませんでしたよね。
安藤:僕らも癒されるよね。
(2014年7月20日、渋谷アップリンク・ファクトリーにて 構成:駒井憲嗣)
安藤紘平(あんどうこうへい) プロフィール
1944年東京都出身。早稲田大学理工学部卒業。〈天井桟敷〉に在籍後、寺山修司の勧めで映画を撮り始め、1970年オーバーハウゼン国際短編映画祭入選、トノンレバン国際映画祭短編部門グランプリなど数多く受賞。パリ、ニューヨーク、ロンドン、東京などの美術館に作品が収蔵される。他にCM作品など多数。ハイビジョンを使っての作品制作では世界的な先駆者で、ハイビジョン撮影を35mmフィルムに変換、『アインシュタインは黄昏の向こうからやってくる』(1994)、『フェルメールの囁き』(1998)など、多数の作品で、ハワイ国際映画祭銀賞、スイス・モントルー国際映像祭アストロラビウム賞、ハイヴィジョンアウォード・グランプリ、マルチメディア・グランプリなどを受賞。2001年、2005年パリにて安藤紘平回顧展が開催されている。
森崎偏陸(もりさきへんりっく) プロフィール
1949年兵庫県淡路島生まれ。17才で高校中退、家出。以来、寺山修司に師事。演劇では音響を主に担当。映画では助監督と記録、写真では紙焼き、新聞・雑誌ではデザインを担当。現在は主に「演劇実験室・万有引力」、「第三エロチカ」、「演劇集団・池の下」、「唐組」などのポスター、チラシ、デザイン、荒木経惟写真集の編集・デザインを手がけている。パルコ映画「ウンタマギルー」「プ」の助監督、高橋伴明監督「愛の新世界」のタイトルデザインなども担当。ほかに白石加代子「百物語」の音響、日本舞踊の水木佑歌、花柳ゆかしなどの演出、SONYブラックトリニトロン、青山こどもの城、寺山修司記念館のためのビデオ監督作品もある。寺山修司監督作品「ローラ」「審判」「青少年のための映画入門」などでは俳優としても出演し、「ローラ」上映のためにベルリン映画祭、エジンバラ映画祭、台湾映画祭などに参加出演している。寺山修司の母、はつの意向により、寺山修司没後、1991年に、元夫人、九篠今日子とともに寺山籍に入る。
映画『リアリティのダンス』より
『リアリティのダンス』
新宿シネマカリテ、渋谷アップリンクにて上映中、全国順次公開
監督・脚本:アレハンドロ・ホドロフスキー
出演:ブロンティス・ホドロフスキー(『エル・トポ』)、パメラ・フローレス、クリストバル・ホドロフスキー、アダン・ホドロフスキー
音楽:アダン・ホドロフスキー
原作:アレハンドロ・ホドロフスキー『リアリティのダンス』(文遊社)
原題:La Danza de la Realidad(The Dance Of Reality)
(2013年/チリ・フランス/130分/スペイン語/カラー/1:1.85/DCP)
配給:アップリンク/パルコ
公式サイト:http://www.uplink.co.jp/dance/
『ホドロフスキーのDUNE』より
『ホドロフスキーのDUNE』
渋谷アップリンクにて上映中、全国順次公開
監督:フランク・パヴィッチ
出演:アレハンドロ・ホドロフスキー、ミシェル・セドゥー、H.R.ギーガー、クリス・フォス、ニコラス・ウィンディング・レフン
(2013年/アメリカ/90分/英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語/カラー/16:9/DCP)
配給:アップリンク/パルコ
公式サイト:http://www.uplink.co.jp/dune/