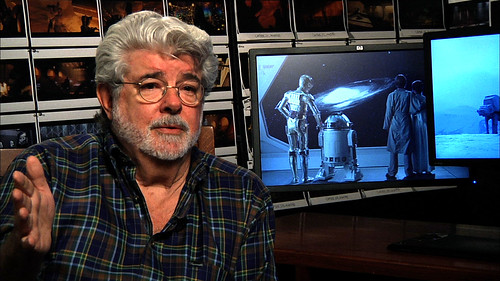映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』上映イベントに登壇した大林宣彦監督
キアヌ・リーブスが製作し、ハリウッドの大物監督やスタッフたちが映画業界のフィルムからデジタルへの変遷について語るドキュメンンタリー映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』が12月22日よりロードショー。上映を記念して、日本映画界を牽引する監督たちによるトークイベントが2日間にわたり渋谷アップリンク・ファクトリーにて開催。初日の22日に、大林宣彦監督が登壇した。
当日は、8mmフィルム、16mmフィルムの個人映画から映画の世界に入り、コマーシャルフィルム、劇映画と長きに渡りフィルムを扱いながら、最新作『この空の花-長岡花火物語』をデジタルで製作したきっかけ、そしてデジタルとフィルムそれぞれの魅力について語られた。
アメリカでデジタルとフィルムはサイド・バイ・サイドだけれど、
日本ではオール・オア・ナッシングになっている
── 『サイド・バイ・サイド』はハリウッドのベテランの監督や撮影監督が出てきますがどのようにご覧になりましたか?
映画のデジタル化は大問題だから、非常に面白く拝見しました。錚々たる人たちが総出演していてすごいなと思いましたけれど、しかし若いなぁと。僕75歳だけれど、ルーカスは新人類のはじまりなんですよ。ストラーロやジグモンドは大ベテランのようだけど、新人類なんだなぁ。新人類という言葉は、PFFでかわなかのぶひろが、手塚眞と今関あきよしのことを言った始まりで、のちに流行語になった。まさにここに出てくる人たちは手塚・今関以降の人たちがしゃべっているように見える。
来年は小津安二郎監督の生誕110年ですが、110年といったら映画の歴史と一緒ですよ。映画の歴史はたかだか小津さんの人生と同じ、たったひとりの人生に値するような期間のなかで、わたしたちは右往左往しながらここにきている。ならばこの大騒動は、黒澤(明)さんや木下(恵介)さんや、60年代以前、もっと言えば太平洋戦争以前の人がここに参加して語れば、もっとデジタル化の未来が面白く見えてくるだろうなと。僕が今日ここに呼ばれたということは、そこの穴埋め作業をやるのか、と思った。
── この映画で語られなかったことを、ぜひ監督の実体験で補完していただければと思います。
ルーカスだっていまや大監督だけれど、彼はデジタル化の犯人だからね。映画のデジタル化は20年前にルーカスが始めた。ルーカスの悪口ばっかり出てくる映画『ピープルVSジョージ・ルーカス』があるけれど、この映画と2本立てやっても面白い。『スター・ウォーズ』は新しい映画ファンを生んだけれど、その『スター・ウォーズ』神話をルーカス自身がめちゃめちゃに壊している、これは何事か、という映画なのね。『スター・ウォーズ』の1作目はフィルムなんです。壊れかけたオプチカル機器(フィルムで特殊映像を作る機械)を2台買って安アパートの2階でB級映画として作った。これが大ヒットしてルーカスがはじまるわけだけれど、その頃僕も『HOUSE ハウス』を作って、「お前が日本映画をダメにした」という張本人だった。
『スター・ウォーズ』ができたときに、宣伝マンの古澤利夫さんがプロデューサーのゲイリー・カーツと僕を引きあわせてくれて、品川のプリンスホテルだったかな、一コマ一コマフィルムをぜんぶほどいてみたのよ。それでゲイリー・カーツに、「この映画はぜんぶNGだね」と、褒めことばを言ったんです。『HOUSE ハウス』も全コマNGで作ったから。
── NGとはどういう意味ですか?
つまりノーグッド、全部合成ズレなんです。ロケットと宇宙空間との間にブルーマットのズレがある。動くものって写すとフッとずれて、合成のバレが出ている。でも映画は時間芸術で、一コマを見るわけではなくて、1秒間に24コマを見るわけだから、そのズレがあるおかげで、ロケットが飛んで見える。だからズレがなきゃ映画じゃないの。だから、それを褒めた。ゲイリー・カーツはちょっと目を白黒させていたね。「まだ不出来ですか?」と言っていたから「いや、不出来じゃないよ。技術的に不出来だから、上映したときにいい映画になったんだね」と言ったんだけれど、伝わらなかったらしい。
ルーカスは最初のエピソード4をデジタルでやり直したんだよね。そこで一コマ一コマのズレをぜんぶなくしちゃったの。どうなったかというと、映画ではなくて、ゲーム映像になってしまったんだよ。良い悪いの問題じゃなく、映画のズレがなくなったことで、感動がなくなっちゃったのね。画としては面白いけど、心に響く感動がない。ルーカスの悪口ばかりで映画が作られたのはそこなんですよ。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
逆に言えば、ルーカスは自分自身の代表作をもめちゃくちゃにしてファンからもそっぽを向かれながらデジタル化を進めた勇気を持った、新しい世代の映画作家だと、褒めることもできる。
フィルムによるオプチカルのズレばかり出る作業を、ズレないようにデジタルに変えてやろうというのがデジタル化で。それは確かに技術的な進歩を遂げた。最後はフィルムで上映するという、入口と出口はフィルムだというのはルーカスたちが始めたことなんです。そのうちに時代が変わって、入口も出口もデジタルにしようというのが現代の問題でね。この『サイド・バイ・サイド』は今年の映画でしょ?
── 今年のベルリン映画祭がプレミアです。
『サイド・バイ・サイド』とはアメリカのいい時代のポピュラー・ソングの題名で、お隣同士仲良くしましょう、デジタルとフィルム仲良くしましょうということでしょ。そういう映画が作られているのに、日本ではオール・オア・ナッシングになっている。入口も出口もデジタル、映画館からフィルムの上映装置がなくなる、富士フィルムは映画用フィルムの製造を止めてしまう。同じ事態を迎えていても、アメリカと日本では違うことを、日本の映画人、文化人はもっとより深く認識する必要がある。
映画は芸術である前に科学文明が生んだ記録装置
映画というのは芸術である前に、科学文明が生んだ記録装置なんです。保存装置まできちんとない限り成立しないものなんです。だからアメリカではデジタルになってもちゃんと記録されるようにやるでしょう。日本では、ただでさえ消耗品で、小津さんや黒澤さんの映画のオリジナルのネガが残ってないという国ですから。日本がデジタル化になったら、今できている名作が全て50年後にはなくなってしまう。
この間アメリカのMOMAの大スクリーンで、60年前の8mmからはじまる僕の映画を上映してくれたんだけれど、これもデジタルのおかげ。そこでムンクの特集をやっていたけれど、僕が『叫び』の前に立っていたら、横にいた男の子が絵に指を触れようとした。ハッとしたら、係のおじさんがいつの間にか横に来て、伸ばした坊やの手を取って、『叫び』の人物のほっぺのところを指でなぞったの。そうしたら男の子は目を輝かせているんだよ。
僕は心配だからキュレーターの人に「こんな飾り方をしていたら、誰かが絵の具を持ってきてモネの絵の上に塗っちゃうかもしれない、そんなことを考えませんか?」と聞いた。そうしたら「大林さん、芸術とは誰もがそういうことをできないほど素晴らしいものなんです。私たちはそういう芸術をここに展示して市民の皆さんに楽しんでもらっているんですから、そういうことはありません」と。子どもが手を取られてムンクの絵に畏怖を感じたから、「このような絵描きになろう」とは思うけれど、この絵を汚そうとは思わない人間に育つ。これが近代美術館の素晴らしいところ。アメリカでは、どんな商業映画ですらネガが保存されることが伝統的にあって、そのことを庶民も知っている。文化の保存ということを同時に考えられる、この文化の違いが残念ながらアメリカと日本にはある。そのことを僕たちある恐怖を持って知る必要がある。これからの若い方たちは保存の方法をきちんと考えてもらうことが大事だ思います。
ルーカスは思想的にデジタル派で、スピルバーグは思想的にアナログ派
── ゲイリー・カーツはなぜフィルムを大林さんに見せにきたのですか?
古澤利夫さんはルーカスがすべて日本での宣伝は彼に任せているというくらいの人で、彼が『スター・ウォーズ』をなんとか日本で成功させようというときに、僕にフィルム全編を見せに来てくれたんです。1970年代は、まだアメリカの新作が日本で上映されるのに少なくとも1、2年かかったんです。僕らはあの『ジョーズ』ですらハワイに観に行った。『スター・ウォーズ』もハリウッドに観に行った。その時僕は『スター・ウォーズ』と『未知との遭遇』を同時に観て、『スター・ウォーズ』はPLAY(遊び)の映画、『未知との遭遇』をPRAY(祈り)の映画だと言ったの。これは我ながらいいコピーだと(笑)。ジョージ・ルーカスは『スター・ウォーズ』をスペース・オペラと言ったでしょう、映画史的に言うとアメリカのフロンティア・スピリットが戦争でダメになって、ホース・オペラ(西部劇)が作れないので、スペース・オペラをやろうとした。
スピルバーグは同じSFでも地球派なんです。地上から見た宇宙。空から友達がやってくる、というのがスピルバーグの世界で、だからスピルバーグとルーカスが新しい時代を作った両巨匠なんだけど、ルーカスは思想的にデジタル派で、宇宙に行っちゃう。スピルバーグは思想的にアナログ派で、人間を考える。なので、この『サイド・バイ・サイド』にスピルバーグが出てこないのは、映画的伝説で考えるならば、非常にまっとうで必然的なことなんです。つまりこれはルーカスの世界の話で、スピルバーグはこの間の『戦火の馬』だっていまだにフィルムで撮っているから。
スピルバーグは1940年代の映画が好きな人で、彼がデビューしたときに「僕は新しい映画なんて何もやっていない。1940年代に憧れたフロンティア・スピリットの映画を、いま新しい技術でリメイクしているだけだ」と言っている。ニューシネマとはフロンティア・スピリットが失われた戦後のアメリカ人たちが、夢を捨ててリアリズムで貧しい歪んだドロドロしたアメリカを描こうというのが始まり。それに対してスピルバーグは、昔の元気なアメリカを新しいテクノロジーで作ろうとした。だからスピルバーグの映画は受けたし、『スター・ウォーズ』を観た時観客は、「ユニオン・パシフィック(『大平原』)だ!」「『ヴァイキング』だ!」って叫んだの。これは40、50年代の映画ですよ。『ヴァイキング』はアメリカをめがけて海を渡ってきた人たちの映画だよね。『スター・ウォーズ』のストーリーもその通りで、勇敢な海賊の息子が奴隷の女と恋をする。つまり、アメリカ人がベトナム戦争は嫌だ、ニューシネマ、現実主義は嫌だ、もういっぺん夢を見ようね、というときに、新しいテクノロジーで、失われたアメリカン・ドリーム、つまりフロンティア・スピリットやヒューマニズムを蘇らせたから、新しい時代が来た。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
MOMAでは、昔からのファンだけでなく若いファンがいっぱい詰めかけてくれる。『HOUSE ハウス』のTシャツ着てブルーレイを持って、30年前の日本の映画、『スター・ウォーズ』と同じ頃の映画、「こんなもの映画じゃねえ」と言われた映画がアメリカで「黒沢清に次ぐ若い監督が現れた」(笑)と呼ばれた。「なぜこんな映画が作れるんですか」と聞かれて「僕はベテランの少年で、メリエスからの映画の歴史を知ってるからできるんだ。君たちがルーカスの前の時代に捨てた機械を使えばこういう映画ができる」と答えた。「この映画で僕の人生が変わった。いつかえらくなって大林さんの映画をプロデュースしたい」と言う若い子がいる。ルーカスやスピルバーグが黒澤さんの『夢』をプロデュースする時代が来たのならば、僕があと15年くらい長生きしたら、彼らがプロデュースしてくれるな、と。そういう風にアメリカでは連綿と続いていくんだね。
科学文明が失敗することで、文化になる
だとすれば、デジタルとフィルムの前の人たちのことも、急ぎ足でも語っておかなければならない。写真は絵画と違って、リアルに物事を記録する。だけど記録したいという欲望が人間のなかにある。絵画だってもともとは記録で、岩山に古代人が描いた絵は記録だけれど、岩山は固いし掘る道具は精度が低いからいやでも抽象化せざるをえない。それが文字になった。文字というのは抽象化された絵画です。だから写真ができたときは、みんなが望んでいたリアリズムがもろに出ているということでびっくりした。映画というのはMOVING PICTURE、それを日本語に訳したのが活動写真です。動くことによって、馬の足が走る時にどう動いているのかが分かったのも、映画のおかげなんです。それまでは誰も知らなかったものを、映画として記録されることによって発見する。
でも、科学文明は壊れるもの。原発が壊れるように、昔から壊れていたんです。例えば有名な話だけれど、荷馬車を撮影していたときに、カメラが突然故障してしまった。荷馬車が行ってしまって、カメラを修理して撮影を再開したらそこにバスが来たのをそのまま撮影した。上映したら、荷馬車が走ってきて突然バスに変わる。記録としては失敗だけれど、何人かの人間が「待てよ、これは面白いじゃないか。ひょっとしたら映画の才能だ」と考えた。日本でも、マキノ省三さんが舞台のチャンバラをそのままフィックスで撮っていた。ところが映画のフィルムはトーキーでは10分しか写せないから、芝居の途中でフィルムがなくなる。そうすると舞台の人はみんなストップするんです。そしてフィルムをチェンジしてスタートすると、その続きをやるんです。ところがストップしている間にひとりの侍がこっそりトイレに行っちゃった。誰も気がつかなくて、出来上がった映画を観たら、チャンバラしている間にパンと人がいなくなる。「親方に怒られる、どうしよう」とみんなが青くなっていたら、マキノ省三さんが「待てよ、これを使ったら忍術映画ができるぞ」と、そこで忍者が消える、という演出が生まれた。だから、科学文明が失敗することで、文化になる。そのことが劇映画を生むんです。
映画とは侵略と戦争の歴史
今作に出てくるマーティン・スコセッシの『ヒューゴの不思議な冒険』でメリエスが描かれていたけれど、彼はもともと奇抜なショーをやっていた商売人で、それをリアルに写すことで拡大していったら、映画の才能に気がついて、これを用いれば自分の舞台のショーがもっと面白くなる、と記録から始めて、記録の壊れたことから新しい表現を発見したのが『月世界旅行』。あの映画では、月にロケットが刺さってるよね。アメリカの思想は侵略なんだ。文明国は弱い国を侵略する。今だって、実際にアメリカが月に行ったときは月面に国旗を立てたじゃないですか。そういうことを読み取っていくことも面白くて、映画とは侵略の歴史、戦争の歴史、メリエスの空想科学映画ですらそこから始まっていることが見えてくる。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
その頃は写実主義といってもモノクロ、やっぱり色がほしい。僕が始めて観たカラーは『母の曲』だったかな。タイトルだけ金魚鉢のなかに色のついた金魚が泳いでいる、金魚を一コマ一コマ色を塗っている。当時トーキーは10本くらいのプリントで日本全国自転車で運んでいたりしたから、プリント一本一本に塗ったんだね。綺麗だった。でもモノクロ映画がカラー映画になったということを誰も進歩だと思わなかった。映画芸術をダメにしたと、今のフィルム派と同じことを言っていた。サイレントの時代に、湖に鳥がいっぱい浮かんでいて、銃を撃って、鳥がとびたっていく。ドーンという音は聞こえないけれど「ピストルが撃たれた」ということをその画で、サイレントでドラマを感じる。サイレント映画は、芸術として完全にできあがっていた。
黒澤明は最後までモノクロで撮っていた。『椿三十郎』で椿の花だけに色をつけようとしたり、『天国と地獄』で煙突の煙だけピンクにしたり、ようやくカラーで『どですかでん』を作ったら「黒澤は色盲か」と批判される。だけどあれはカラー映画の歴史のなかの大変な傑作です。つまりリアルな色ではなく、画家のように芸術的な色をつけることで黒澤さんがようやくカラーにした。
無声映画がトーキーになったときだって、誰も進歩だと思わなかった。徳川夢声のような弁士さんはクビになるし、多くの俳優が仕事を失った。いい顔だったのに、しゃべったとたんがっかりした、ということが起きる。坂東妻三郎さんが始めてトーキーで語った映画を子どもの頃観て、びっくりした。すごい豪傑が刀を抜いて「俺は!」と甲高い声でしゃべる。その声をいっしょうけんめい枯らして、迫力のある声を出すようにして名優になった。これはトーキーを乗り越えた人だよね。チャップリンも最後までサイレントで通した。でも最後彼がトーキーを作った『ニューヨークの王様』は和田誠さんが言う、名言集の映画です。
黒澤もチャップリンも、素晴らしいトーキー、素晴らしいカラーを作ったけれど、世界でいちばん最後にです。小津安二郎はワイドを撮らず、スタンダードのままだった。ということは、世界をリードした芸術家たちが、最後にそれをやった、というくらい、サイレントも無声映画もスタンダードサイズの映画も、芸術として完全に完成されていた。だとすれば、今のフィルムも芸術として完成されている。失われることは悲しい、というのもまっとうな意見だ。だけどそれがデジタルになってどうなるかといえば、いつかそれが普通になる。それは科学文明が発明した芸術の当然の運命なんです。僕は日本でも最大のフィルム党で、ついこの間までフィルムで編集していた人間だから。でも『この空の花』で時代を察してすぐデジタルにしたんです。
デジタルでやる以上は、フィルムでぜったい撮れないものをやるべき
── 『HOUSE ハウス』はオプチカル処理で合成していたんですよね。ルーカスは『スター・ウォーズ』で早くもデジタル化しましたけれど、大林監督はやっと『この空の花』でデジタル化になった。この違いはなんだったのですか。
僕と同年輩の島村達雄という人がいる。『三丁目の夕日』など今のCGを使った映画を作った白組の社長です。『HOUSE ハウス』の頃は年中一緒に作っていて、僕の昔の映画を観たら、タイトルにみんな白組と出てきます。1990年、彼が僕のところに来て、「CGが本格化されて、大林さんのやりたいことがぜんぶスタジオでできますよ」とあんまり薦めてくるから、冷静になるわけだ。「新しい技術は君に一任するから、ここで決別しよう、僕はこれから見捨てられるフィルムで最後までこだわる」と言ったんです。その後白組は大ヒットを飛ばすし、僕は相変わらず自主映画を撮っている(笑)。
── 島村さんがあまりに薦めてくるので、大林さんのデジタル化が遅れたんですか。
同じことをふたりやる必要はないの。僕と高林陽一くんと、飯村隆彦くんだって、当時8mmをやっているのは3人だったから、同じことをやるのはもったいないので、僕はコマ撮り系を、高林くんは長回し、飯村くんは現代アートをやる。そのおかげで高林くんは個人映画を撮り続けることができたし、飯村くんはニューヨークで芸術家というより映画を作る市民として幸せに暮らしている。これは文化の違いだけど、僕は僕として日本映画の中でパイオニアの仕事をしたと思っています。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
── 『この空の花』をデジタルでやるというきっかけは?
撮影監督の高間賢治さんから「3年ぶりにフィルムでやる」という年賀状がきたりするくらい、日本はみんなデジタルになってしまった。山田洋次さんは「フィルムなくなったら映画撮りません」という。これは画質だけの問題じゃなんです。日本の映画界は、NG率は2倍半なんです。
── 2時間の映画だったら5時間分のフィルムがストックしか組まれないと。
役者が芝居する前と、カットという声の後、捨てるところを残したら、1本の映画でNGを出せるのは2回。だから、小林桂樹さんのようなベテランの俳優さんと仕事をすると、現場に台本を持ってこない。句読点までぜんぶ頭に叩きこんでくる。役者が自分の芝居でNGを出したらギャラなし、クビになる。山田洋次さんはその緊張感のなかでしかヨーイスタートの声をかけられない。フィルムをのんべんだらりと使って緊張感がなくなったら、演出も演技もできない。
オーソン・ウェルズは、誰も金を出してくれなかったから、ある映画ではNGでも一回しか回さない。その緊張感がオーソン・ウェルズの名作を作っているし、大島渚さんが最後の映画を撮られるときもそう。大島さんのあの「ヨーイスタート」の声の気合があるから撮れる。そういう意味では、デジタルとフィルムでは演出が違うし、演技も違う。ということは、映画がまったく違う。どっちがいいか悪いかは政治家と経済家にまかせておけばいい。真の芸術家は、どっちにも良さがあるはずだ、というのが仕事なんです。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
僕がその長い間なぜデジタルをやらなかったかというのは、フィルムの人間がフィルムの味を出したくてデジタルをやってるからなんです。それはダメだと思う。デジタルやるからにはデジタルの良さを発見したらどうか、それがデジタルをやることじゃないかと。僕はそういう主義なんです。だからデジタルの良さとはなんだろうと、ずっと考えてきた。チャップリンや小津や黒澤のように、デジタルが使えるまで待ってやろう、つまり故障待ちですよ(笑)。
でも誰も故障させないんだ。映画のように綺麗に使っているから。だから僕は大学の教授を始めた。学生はデジタルで作るのでいっぱい失敗例が生まれる。失敗例を可能性と考えるから、勉強になったね。そこからカンヌまで行ったのが、河瀨直美くんですよ。先生が高林くんだったから「君が8mmやデジタルでやっていることをそのまま世界に持っていけばみんなびっくりする」と言ったそうです。そのことが今の時代に大事なこと。
メーターマンもカメラにしてしまった
『この空の花』はフィルムで撮ったら20億かかります。でも予算は10分の1以下です。僕がフィルムにこだわる作家だったら作れなかった。よし、デジタルでやろうと、黒澤組の木村大作の弟分の加藤雄大を起用した。「カメラが5台いる、撮影部何人いる?」と聞いた。「VEとメーターマン入れて20人弱かな」と彼は答えた。「デジタルは学生を見てるとひとりで回してるよ、カメラマン5人でいいんじゃない?」と僕は言った。加藤雄大も「分かりました、やりますが、三脚やバッテリーを抱える人間がいないので全編手持ちでやります」ということで、最初のロケは全部手持ちだったんですが、結局全部使わなかった。
いよいよ本撮影ということになったら、三脚で撮っている。聞いてみたら「勉強してきました、デジタルは三脚ごと担いだら楽なんです」それはそうだろうと(笑)。現場行ったらメーターマンがメーター持って測っているので「フィルムみたいに撮って一週間経たないと分からないものなら心配だけど、デジタルならモニターでカメラマンが全部見られるからいらない」と言うと「カメラ5台の光量をぜんぶ合わせておかないとバラバラになります」と彼が答えた。カメラ5台を使うなら順光もあれば逆光もあって、絞りが二つぐらい違う。それをメーターマンが合わせても意味がない。そこで「あんたカメラ回したくないかい?」とメーターマンもカメラにしてしまった。だからどんどん早く撮れるし照明がいらないのがデジタルの良さなんです。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
昔、うっすら暗いところで女人が立っている綺麗なシーンを撮りたいと思っていたが、フィルムでは映らない。いつか映る時代がくればいいとみんなが言っていて、せっかく理想の画が撮れる時代が来たのに、そこにライトを持ってきて当てる。バカじゃないかと。カメラがライト以上にものを写す能力ができたのがデジタルなんだから、そこにライトを当ててテレビみたいにしてしまう。デジタルで映画を撮るなら照明はいらないんだ。
だけどそこは組合の問題にもなる。ここに照明部やメーターマンさんがいたら「俺の仕事をなくした」と怒るでしょう。でも、活弁士がいなくなったように、声が出ない俳優が失業したように、科学文明のなかで生きている以上しょうがない。照明を工夫して自由に5台のカメラを動かせたから『この空の花』は撮れた。
みなさんよく考えてほしいのは、フィルムで撮るものはデジタルでぜったい撮れません。同時に、デジタルで撮れるものはフィルムで撮れません。だからデジタルでやる以上は、フィルムでぜったい撮れないものをやるべき。そうしたら新しい映像文化が生まれる。それが科学文明とつきあう僕らの作り方です。
『この空の花』はフィルムで撮ったら5時間の映画になる
ただ、大事なことは保存について。作品を保存するためには、やっぱりフィルムがいいんです。デジタルで撮られたものも、上映はデジタルでいいから、文化を保存するためにフィルムで保存する。正直に言えることは、ポスプロも撮影もデジタルで、しばらく新しい映像の研究を楽しんでやりましょう。ただし保存に関してはデジタルでは保障がないからフィルムを使う。あと30年くらいはデジタルが面白くて時間が足らないね。いまどき「フィルムじゃなきゃ撮れません」なんて時代遅れの人間はどこかへ行きなさい(笑)。
── 『この空の花』に20億かけるプロデューサーがいたら、フィルムでできたんですか?
できます、ただ内容や演出はまったく違っていたでしょう。あれだけの内容をフィルムのペースで撮ろうとしたら5時間の映画になる。逆に『人間の証明』をデジタルで撮ったら3時間になりますよ。フィルムは粒状性のあいまいなメディアだから、光と影のなかで想像ができて、コップを1分寄って撮るだけでもいろんなことが描ける。でも、デジタルは1分撮ってもただ水が映っている、それだけ。だから10時間の映画は2時間になる。
『この空の花』は忙しくて目がまわる映画で、デジタルはフィルムよりもスーパーがよく見えるから多用できる。撮影条件だけじゃなく、演出もガラっと変えました。311の後、切羽詰まったときに、誰が10時間の映画を観ますか、せいぜい3時間ですよ(笑)。そういうことも全て含めて、きちんと計画的にやってみようと、デジタルで作ることに踏み切りました。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
── 『この空の花』に照明部はいたんですか?
面白いことに、加藤雄大は映画的に撮りたい、と、いいレンズをデジタルカメラにつけるためのマウントを作った。それで甘い、フィルム的な画が撮れるようになった。そのかわり、絞りが4倍暗くなった。だから、せっかくデジタルなのに照明が必要になった。これは俺のミスでした(笑)。だから今度やるときは「マウントなしにしよう」と言います。結局照明はいらないと言いつつ、20人ぐらい必要になりました。
── カメラは何を使ったんですか?
ありとあらゆるもの。ホームビデオも使ったよ。結局いちばん金のかかった4Kはマウントをつけたために、映画的になりすぎて、そこだけ重厚感がですぎるのであまり使えなかった。
── フィルムに近づけてデジタルでやるというのはナンセンスだけど、加藤さんは身についたカメラマンの習性で、映画とはこうだ、という考えがあるから、どうしてもフィルム的なものをデジタルで撮ろうとしたんですね。
それが彼の映像の持ってるクオリティだから、それは彼の財産でもある。もうひとつ、僕の昔のパートナーの阪本善尚くんは、映画人というよりも科学者なんです。フィルムはヨウ化銀だから、オプチカルかけても現像しても毒がでて環境破壊になる。デジタルにはそれがないという理由で彼はデジタルにした。そのかわり、彼はフィルムが好きだから、デジタルでフィルムと同じクオリティのものを作ろうとパナソニックと組んだ。パナソニックが開発した映画モードはぜんぶ阪本くんの映画的財産なんです。でも「分かるけど、それは阪本くんがやってくれ。俺はそういうあいまいなことをやらん」と決別しているんです。
デジタルで1万人のアマチュアが作って20本いい映画ができる方がいい
── 次はフィルムとも決別した、デジタルでしかできないことをやりたいですか?
そう、フィルムでぜったい撮れないデジタルの良さを出すのが僕の仕事。それは『HOUSE ハウス』と同じく経験があるから言える。僕は、メリエスの頃からの映画を同時に体験できた最後の世代なんです。『この空の花』も、日本の制作状況、上映状況のなかで、フィルムも作りました。
── 最初の公開はフィルムで上映したんですよね。
スバル座ではフィルムで上映しました。そこでデジタルで撮ったと思った人はほとんどいなかったね。シネコンではDCPでやりました。アップリンクではブルーレイです。ブルーレイは全国どこでも上映できる。上映効果はお客さんレベルで観ると変わらない。3種類比べてみたかったんです。でも、いちばんよかったのはDCPだね。元がデジタルだったら、終着駅もデジタルがいい。画はほとんど変わらないけど、音がフィルムよりDCPのほうがいい。
それとなにより良かったのは、デジタルになったことにより、自主配給ができます。これまでは興行師にまかせてサヤを取られるという悪習があったけれど、DCPかブルーレイを持って直接劇場に行けば、売上半分が収益になる。大劇場だけじゃなく、インディーズにとってもありがたい。それと制作費が10分の1で同じものができる。誰でもできるのはいいことです。なにも制度化する必要はない。良いものになるかどうかは別の話だけど、10人のプロが撮って5本いい映画ができるというのもいいけれど、1万人のアマチュアが作って20本いい映画ができるなら、結果いいじゃない。
僕も撮影所から見れば単なるアマチュア、あるいはコマーシャル屋です。そういう人たちに作るチャンスができた。才能のある人が企業や商業主義や芸能界やタレントプロダクションの重圧を越えて自分の芸術表現ができる。これはフィルムという文化が失われるという業界内の小さなことを越えて、たいへんな可能性がある。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
昔コッポラが「いつか一台の小型のビデオカメラが映画の歴史を変えることがくるかもしれない」と言った。彼はそれを信じて『地獄の黙示録』で破産騒ぎまでやった。そういう信じられる未来があるからやれる。老成した映画を撮っていればいいのに、僕がこんなバカなことができるのは、僕の続きに若い人たちがそれを乗り越えて、いつか『この空の花』が古典的な名作だと言われる時代が来ると信じているから。そういう大きな時代の流れの中にフィルムが失われていくということがある。それをどう活かして楽しんで未来を豊かにしていくかということを考えたほうがいいと思う。
ただし、科学文明が発達しすぎると、原発の問題でいえば、もっと安全な原発作ろうよと考えるほうが健全だということにもなる。その考え方は危険だから、ここで原発やめよう、ということのほうが大事だと、そこで難しい選択がある。映画がデジタルになるということも同じです。可能性が広がるけれど、原発の故障と同じ怖さも僕たちは持っていなければならない。それは保存の問題で、原発で人類の命の保存が危なくなるように、デジタル化で映画という文化の保存が危なくなることは間違いなくくる。だからもっと慎重に考えることが必要です。
『この空の花』はキュビズムで作った〈シネマゲルニカ〉
──『この空の花』はどうやって保存を考えていますか。
これはもうフィルムがあるから。フィルムだけは残るだろう。僕ら映画人は想像力がたくましいから、この間トンネルが壊れたときに、日本の高度成長期のスクラップ・アンド・ビルドの思想の寿命がきたと思った。
もし今生まれているデジタル作品がデジタルだけで保存されていたら、50年後機械が壊れて映画がぜんぶなくなる恐怖がある。あのトンネル事故をなくすくことは、僕にとってデジタル化でなくなることを防ぐためにどうするか考えることに繋がる。映画は社会の暮らしとジャーナリズムにあるので、『この空の花』も芸術のジャーナリズム。
映画は、記録装置が壊れることで記憶装置に、あるいは情報と物語装置に変わっていった、ということに、面白さを感じています。そのなかで、僕たちがいま考えなくてはいけないのは、映画の面白さは20世紀のジャーナリズムになっているということ。小津の人生が映画の歴史だとすれば、ピカソの人生だって映画の歴史です。あの人は写実からはじまっている。老年になっても写実派として描いていたら名巨匠になって人生としては成功していただろうけれど、彼はキュビズムを始めた。横顔に眼が2つついている絵は、当時子供が書いたようだと非難された。『HOUSE ハウス』やルーカスの『スター・ウォーズ』と同じ目に遭っていたんです。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』より (c)2012 Company Films LLC all rights reserved.
だけどピカソは、もし赤ん坊が絵を描いたら、お母さんがふたつの眼が僕を見てくれている、と横顔にだって後ろ姿にだってふたつ眼を描くだろうと考えた。赤ん坊は存在そのものが芸術的なんです。だから赤ん坊が絵を描けたら、キュビズムになる。芸術は心で感じるものだから。ピカソは赤ん坊の生命力に憧れて、自分の芸術を活かそうと、キュビズムに向かうんです。
『ゲルニカ』という傑作は、ピカソの祖国のゲルニカという街に1939年ドイツ軍が攻撃した、つまり長岡と同じように、あるいは日本のあらゆる都市と同じように、崩壊して人が死んだ里を描いています。もしこれを写実派で描いていたら、目を背けたい、忘れたい記憶として風化してしまう。しかも、スペインと関係ない日本では、遠い街の戦争のことなんか知らないよね。ところが、『ゲルニカ』という絵で描いたからこそ、面白くて、不思議で、美しいから、風化しない。普遍化して、世界中のふるさとの崩壊の後として記録して、小さな子どもでも分かるように「昔戦争があった、怖い、戦争なんかない時代にしよう」という平和への祈りへ繋がっていく。芸術のジャーナリズムは風化しない。人は忘れるから生きていけるということもあるけれど、日本のように戦争を忘れて、なかったことにしたような怪しげな平和を作ってしまうこともある。そのことを描いたのが『この空の花』です。
デジタルでやるなら、一回観ても分からない、キュビズムで作ろうと思ったの。でもあの映画を観た4歳の子供が父親に聞いたそうです、「お父さん、僕いま生きてるの?」って。この一言で僕はいいと思う。子どもって生きてるのが当たり前だけれど、あの映画を観て、父親に聞いてみたくなった。その子は命を感じてくれたから、育っていくなかで、いつかあの映画が示そうとした平和への祈りを彼の人生のなかで生かしてくれると思う。
だからこの映画は、20億の出資者がいて、写実派で描いて、誰もが一度観たらよく分かって大ヒットするよりも、シネマゲルニカと僕は称しているんですが、自主配給で苦労しながら上映していくことが、この映画がいちばん願う映画としての価値以上の、芸術の本来の目的である平和を作っていく力になる。
ゴッホが「僕の絵がいちばん幸せなのは、場末のレストランにかけてあって、そこで安い料理を食べた人間が僕の絵を見て『今日の料理はうまい』と思ってくれること」だと言った。自分の耳を切り落して自殺した壮絶な芸術家ですら、芸術の役割をそう思っているんです。暮らしのなかで、どう役に立つか、ということ。だから、この映画がいまの日本の映画界で認められなくても構わない。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』上映イベントの会場・渋谷アップリンク・ファクトリー
── なるほど、ゲルニカなので、フィクションでありドキュメンタリーであり、ナレーションがあり、カメラに向かって俳優が喋り出し、実写にアニメが混ざり、台詞に加えてテロップで読ませる。映画のデジタル化ということでは『ゲルニカ』の前に立った子どものように感じられるか、という感性が問われ、お客さんもそこに対応していかないといけないですね。
子どもは未来人だと思っています。中学校や高等学校で随分上映されて、たくさん感想をもらいますが、誰も分かっているわけではない。分からないところから始めている。大人は分からないものが前にあると拒否する。でも、子どもは分からないから考えようとする。それが未来人。そして映画館に集まる観客は、昔から子どもだった。映画のなかで映っていることは実は分からないことばかりなんです。でもそれを分かろうするのが映画。だから映画は学校だった。いま間違った大人が映画を見すぎていると思う。
── 間違った大人に合わせた映画を撮ろうとしている。不思議なことや分からないことをそぎ落として、「これだったら分かるだろう」とちょっと上から目線の映画が多いですね。
でも映画館に入るとみんな子どもに戻る。それが映画のいいところです。子どもは喧嘩はするけど戦争しないからね。
── あと30年、とおっしゃいましたが、これからも作り続けてください。
僕だって100歳の新藤兼人さんが作り続けてくださったから、『この空の花』を作れたんだし、先輩がいるから後輩もがんばれる。ここで僕が「フィルムでなきゃ」と老成していったら未来の役には立たない。たぶん小津さんや黒澤さんやジョン・フォードやウィリアム・ワイラーが『サイド・バイ・サイド』に出てきたらそうおっしゃったと確信を持って言える。
さらに言えば、小津や黒澤がデジタルを使ったらすごい映画を作る。伝統的な目線をわざわざずらして家族の崩壊を描いた小津安二郎がデジタルを手に入れたら、どういういたずらをして、日本の原発家族を描くかを考えたら、僕たちもそういう映画を作らないといけないのよ。黒澤や小津に憧れる、ということは今デジタルでそれをやるということです。
(聞き手:浅井隆 構成:駒井憲嗣)
大林宣彦 プロフィール
1938年広島県尾道生まれ。3歳の時に自宅の納戸で出合った活動写真機で、個人映画の制作を始める。上京後、16mmフィルムによる自主制作映画『ÉMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ』が、画廊・ホール・大学を中心に上映されジャーナリズムで高い評価を得る。この頃からテレビコマーシャルの草創期に本格的に関わり始め、その数は2000本を超える。1977年『HOUSE ハウス』で商業映画にも進出。故郷で撮影された『転校生』(1982年)『時をかける少女』(1983年)『さびしんぼう』(1985年)は”尾道三部作”と称され親しまれている。2011年3月11日を受けた最新作『この空の花-長岡花火物語』は2012年全国順次公開中。2004年春の紫綬褒章受章、2009年旭日小授賞受賞。2012年12月、ニューヨークのMOMAで初期の8ミリ作品からの回顧展が行われた。
映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』
渋谷アップリンク、新宿シネマカリテにて上映中、他全国順次公開
監督:クリス・ケニーリー
プロデューサー:キアヌ・リーブス、ジャスティン・スラザ
撮影監督:クリス・キャシディ
出演:
キアヌ・リーブス
マーティン・スコセッシ
ジョージ・ルーカス
ジェームズ・キャメロン
デヴィッド・フィンチャー
デヴィッド・リンチ
クリストファー・ノーラン
スティーヴン・ソダーバーグ
ラナ&アンディ・ウォシャウスキー
ラース・フォン・トリアー
ダニー・ボイル
公式サイト:http://www.uplink.co.jp/sidebyside/
公式twitter:https://twitter.com/sidebyside_jp
公式FACEBOK:http://www.facebook.com/sidebyside.jp
▼映画『サイド・バイ・サイド:フィルムからデジタルシネマへ』予告編