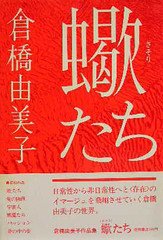文筆家の五所純子が一人語りにより縦横無尽に書評を繋げていくイベント『ド評』。渋谷アップリンク・ファクトリーにて毎月最終火曜日に行なっているこの企画、第五回は『食欲』をテーマに、およそ一般的に語られる『食欲の秋』といった形容から連想される作品とはかけ離れた 本がセレクトされている。この回に登場した書籍の一部を紹介するとともに、一見関連のなさそうな雑多な書物と書物の関係性を明らかにしていく彼女の語り口を再度堪能してみて欲しい。
天真爛漫な食欲の旺盛さに、恋愛感情の自由さや旺盛さそのものを見て取る
『オリーヴ・キタリッジの生活』
著:エリザベス・ストラウト
翻訳:小川高義
早川書房
アメリカ北東部の腐ったような田舎、なんの文化もないような暗い港町に住んでいる夫妻の妻、オリーヴ。そこでの日常で起きる些細な夫婦げんかの醜悪さだったり、浮気未然の恋が終息していく様子だったり、すべての編にオリーヴ・キタリッジという女性が登場します。オリーヴが主人公の章もありますし、ほんの断片、とても奇妙な顔の出し方もあれば、これは後でまとめるときにオリーヴのことを加えたんじゃないかなというような編もありますが、とても印象に残る顔を出し方をします。中年から老年になっていくひとりの女性オリーヴが統一するものとして物語を持続する仕組みになっていますけれども、些末な日常を書いているようでありながら、どんどん日常が歪んでいく。その中に「飢える」という章があります。ある若いカップルがいて、なにをするでもなく、小さな商店で万引きをしていく。それをオリーヴは見つけて、でも何も言わない。だけど、そのカップルの女性のほうがキタリッジ夫妻は気になってしょうがない。ぎすぎすに痩せていたんです。オリーヴは夫とともにドーナツと牛乳を差し出して、半分でいいから食べなさいという。だけど、そのニーナという名の娘は食べようとしません。
「飢える」ということは、ストレートに素直な意味をとれば、食べるものも食べられず、生命の危機に陥るような飢餓状態を指すわけですけれど、この娘にとっては、おそらく精神的なものであろうと。飢えるというのは、必ずしも体の状態だけでなく、精神の飢餓状態に陥ることも指す。ニーナの場合は精神の飢餓とともに実際体も痩せていき、見知らぬ老人夫妻に心配されるまでになっていく。
その食欲が起こらない状態、起きても嘔吐するとか、または過剰な摂取をしては吐き下し、束の間の精神的な休息を得るのを滞りなく繰り返してく病もありますよね。いま飢えるといったときには、そういったなにか抽象的な、内面的なことのほうを指すんだろうなと思います。
『風の又三郎(脚本集 宮沢賢治童話劇場)』
編:日本演劇教育連盟
国土社
宮沢賢治の「飢餓陣営」、これはコミックオペレットという劇作ですね。幕が開き、戦争をしているわけですが、「もう八時なのにどうしたのだろう バナナン大将は帰らない」「ああただひときれこの世のなごりにバナナかなにかを食いたいな」という繰り返されるセリフがあって、ダジャレですけれど、永遠に戦争の攻防が果てしなく続いていくことと、食えないことの先の見えなさ、果てのなさが読まれた劇作です。
『イメージの文学誌 物食う女』
監修:武田百合子
北宋社
食にまつわる劇作や小説、あと絵画も少し収められています。このアンソロジーが優れているなと思うのは、テーマごとに食の位相が変わって見える。飢餓の時代のあとに飽食の時代がくると食の意味も変わります。たとえば怪奇幻想文学、奇想をともにするような文学で人がよく食われていますけれども、さてそういったところで「食べる」という意味は何なのかと考えたりもします。武田百合子は武田泰淳の妻でもありますが、武田泰淳といえば私は『ひかりごけ』を教科書で読みました。洞窟のなかで生死も解らない状態に置かれた男たちが先に死んでいった人たちの人肉を食うという、極限状態に置かれた人間を描きながら倫理を問う作品として話題になったと思います。子どもの私としては、人が人を食べたというところしか覚えていないくらいショッキングでした。この武田泰淳と武田百合子という人は文学的なある共犯関係にあった夫婦だとも言えると思います。富士のふもとに暮らして、武田泰淳が病んで亡くなった後に、『富士日記』というエッセイ集というのか日記文学が発表されました。この『物食う女』のなかにも武田泰淳の作品が入っていて、『ひかりごけ』は男が男を極限状態で食料にしてしまう人間心理を倫理的に問いかけた作品でしたが、この表題になっている『物食う女』っていう作品が武田泰淳の小説で、なんというか、『ひかりごけ』に比べれば余裕です。
ふたりの女性の間で、なんだか悩ましげな恋というのか、煩悶する男の物語です。
この主人公の男性は、天真爛漫な喫茶店で働く凡庸な女給の食欲の旺盛さに、恋愛感情の自由さや旺盛さそのものを見て取ります。食と恋愛を重ねてみることは飢餓の心配をしなくてもよい環境になったときに普遍化したことなんじゃないかなと私は思うんですが、どうでしょうね。恋愛感情を通り越して食欲と性欲の本質的な直結みたいなことが言われますけれども、この作品も、本能的なものを剥き出しにした恋愛小説ではありませんが、恋愛感情と食欲の奇妙な交錯を感じされる描写がなされているのと、もうひとつ。女性そのもの、ここでは後者の天真爛漫な女性そのものが自然物の豊穣な恵みのように描かれているんですね。女性が果実に喩えられやすいのは古今問わずですが、新聞社勤めの堅い女性のほうに男が体を求めているくだりがないのですが、後者の女性にはとにかく食べ物屋に連れていきたがる。とんかつを食べ、トマトジュースを飲み、カツレツが挟まったおいしそうなパンを食べ、そしてアイスキャンディーを映画館で舐める。とにかく食べ物とともにあって、最後に無体な接吻のせがみ方をする。
『官能小説用語表現辞典』
編集:永田守弘
筑摩書房
一家に一冊あるといいと思います。よく女性の体や女性性そのものが果物に喩えられたりですとか、なかでも水蜜桃は多いですけど、そういう描写にバリエーションが出てくるのも時代状況の変化は大きいのかなと思います。食べ物というのは様々な慣用句で使われると思いますが、なかでも性的な意味合いをどれほど含んでいるのか。この本にはいちじくや貝、牡蛎の汁や洋梨というのをはじめとして、およそすべての食品がここに出てくるのではないかと思うくらいです。面白いのは用例がそれぞれ出ているところです。
武田泰淳という作家における変化ということではないと思うのですが、ふたつの作品を見たとき、男が男の肉を食らうときのシチュエーションが指し示すものはとても過酷な追いつめられた人間たちの最悪の選択、その心理と倫理というものだったわけですけれど、女と男の間に食欲がからめられたときには、いまではオーソドックスな恋愛の物語だったという感じがします。
食においては、ゴスロリ少女より、ロハスのほうの人たちのほうがラディカル
『恋愛太平記』
著:金井美恵子
集英社
『若草物語』が古典にあるように、『恋愛太平記』は現代の四姉妹の恋愛模様や結婚、生活や人生が描かれた小説です。昔は金井美恵子の文体を冗長だと言った批評家たちもいたそうですが、修辞句が連なって長くなる構文そのものが、当時の文学に批評的な効果を与えていたと思うんですけれど、読んでいてとにかく楽しいのは、食べ物や服の生地やお皿のかたち、そういった日常の些事に見えてしまうディティールが書きこまれていること。それがある種の批評家たちには、なんでこんな陳腐な日常の些末なことを書いているんだ、退屈だということになってしまったわけでしょうが、単にそれを記述しているというわけではなくて、その細部が全体の描写になっているということだと思います。だからたとえば推理小説において探偵がトレンチコートやプラダのスーツを着ていると書かれているような人物設定とは決定的にちがう。姉妹が延々とトイレットペーパーの話をしていたり、コーヒーはインスタントでいいのかそうでないのか、そこから連想ゲームのようにファンデーションの話題へと会話が流れていき、そうやって永遠に横滑りしていくのではないかというなかで四姉妹の姿があらわれてくるのが、読んでいて気持ちいいのです。
『兎』
著:金井美恵子
集英社
同じ金井美恵子の時期を遡って、もう少しえぐい少女小説とも呼べそうな『兎』という短編集があります。この中の表題作「兎」の冒頭には、「書くということは、書かないということも含めて、書くということである以上、もう逃れようもなく、書くことは私の運命なのかもしれない」という、作家宣言と呼びたくなるような一文で始まるお話なんです。
成人女性が散歩の途中に雑木林のなかに空き家を見つけて、そこに兎がいるんです。『不思議の国のアリス』がそうだったように、兎は人間の言葉を喋ります。「あなた、兎さんですか」と聞くと「すっかりそう見えるでしょ、私はほんとは人間です」、と自分の正体を明かして、彼女にその来歴を語っていく物語です。
ちなみに彼女は兎なんですけれど、小百合という名前を持っています。兎は自分が凡庸な名前であることをとても嫌っていて、鬼の百合とか姫百合だったらよかったと嘆きます。自分は他人とは異なるべきだ、自分の凡庸さに耐えられない、もっといえば、他者に名づけられたこと自体が耐えられない。これも文学で描かれる少女というものの特徴かもしれません。他人とはちがう、もっと過剰で極端な存在であったはずだろう、と。そういう意味で、この兎は小女性が強調された存在だと思います。彼女は父とふたりで暮らしていました。母と姉が生きている間は、この父は「飽食と睡眠を好む赤ら顔の豚」と揶揄されていますけれど、この少女だけは強烈なファザコン性をほのめかしながら父との暮らしを回想していきます。なにをやっていたかというと、父親は小屋に篭って兎をどんどん殺していたのです。その皮を壁に貼りつけて、兎料理を家族に振る舞うのがいちばんの幸福であったと。内蔵まできれいに全部使って、兎を猟奇的にさばく父。血の汚点だらけの家に彼女は暮らしていたんですけれど、やがて父と娘ふたりの生活が始まって、娘自身も兎に手を下すようになります。
「兎の血で陰毛をきれいに揃えるのが好きだ」、という少女像と猟奇性。少女は現実に対する離反感が強いために残忍さに陥る、というそういった少女像の世界だと思います。かっこいいんですよね、長い耳のついたフードと仮面を被って暮らすようになるんです。一時期、渋谷のセンター街にもいましたよね。あれは私はとても好きでした。ギャルがアニマルになっていく。家出少女が問題になったときに、あの飢餓感はなんだったんだろうと。さっきの「飢える」の話にも繋がりますけど、その家出少女の路線って、やっぱり拒食症ですとかリストカットですとか、体の線がどんどん細くなっていって、飢餓を点滅させる方向性がひとつ強かったと思うんですけれど、もうひとつ。ジベタリアンっていうんですかね、自分の土地じゃない、日本の土地に対する私有財産制とかにも喰い込む話だと思うんですけれど、公の地べたに座り込んでトライブを形成するような不良家出少女像が出てきて、こっちは痩せ細るのとは逆に「盛る」方向性だと思うんですよね。耳がついたフードを被っている人もいましたよね。たぬきやパンダ、挙げ句の果てにはピカチュウまでいましたけれど、ヤマンバギャルのメイクも同じ系統ですよね。痩せ細って飢餓感を点滅させてしまう像よりはよっぼどふてぶてしく、また見た目がまるでPファンクのようなパワフルさを持っているのが私はとても好きでしたが……彼女たちはどこへ行ったんでしょうね。
主人公の女性は、自分はだんだん視力を失いつつあるんだという兎の独白を聞きながら、その雑木林に行くこともなく、しばらく暮らすんです。けれどずいぶん年月がたってから雑木林におもむいた主人公の女性は、少女が着ていた生皮のパッチワークを着こみ、少女と同じようにじっとうずくまる。兎たちの死体と少女の死体と、その少女が着ていた兎のフードコートを来てうずくまる「私」というのが最後に残されるんです。これを皆さんはどう読むんでしょうか。成熟したひとりの女性が、その少女性に舞い戻って閉じこもる話だとも読めるんですけど、不思議と私はそうは感じなかったんです。それまで書かれてきた少女性に隣接しながらも、やがて彼女はこの小屋から出ていくだろうというような読後感を得たのですが……どうでしょうね。
彼女は小屋のなかで兎たちの死体の傍らにずっと息を詰めているだけなのでしょうか。少女性と言われるものの問い自体をしめした完結だと思います。それを若い金井美恵子が書いている、ということの意味と合わせて、『兎』は何度も読み返したいです。
『蠍たち』
著:倉橋由美子
徳間書店
少女に限らず少年少女の残酷性というものを描いた、これも傑作です。倉橋由美子も『聖少女』という、まさに少女小説という日記文体の作品を書いていて、少女の自己愛の充満する世界を日記文体で表しているのが『聖少女』です。しかしどうして少女小説というのは女性たちによって自ら書かれるんでしょう。それは、先ほど言ったように、内面を担保するためのものなんでしょうか。そこから出られない、ひょっとすると窮屈な、息の詰まるような、内面性を守るために作られたお城のようなものなんでしょうか。『兎』の白い装丁と『蠍たち』の赤い装丁が対になってるみたいで、並べると壮観じゃないですか? 『蠍たち』を書いた倉橋由美子に『私の読書散歩』というエッセイ集があります。ここにおさめられたエッセイや批評を読んでいると、当たり前ですけど、作家が自己愛に耽溺するように書いていたということではなく、非常に醒めた認識をもって書いていたということがわかると思います。
『兎』の少女の形象はたしか吾妻ひでおのマンガにも出てきますよね。『兎』は『物食う女』にも収録されています。武田百合子は食べることが好きだったようで、『富士日記』に限らず「文藝別冊 武田百合子 天衣無縫の文章家」におさめられた武田泰淳との日々を綴ったエッセイのなかでも、食に関する記述は多いですね。
武田百合子といえば、「クウネル」という雑誌の創刊号に、武田百合子と娘の武田花の対談が載ったんです。「クウネル」は「ストーリーのあるモノと暮らし」がキャッチコピーでしたっけ。ロハス雑誌になぜ武田百合子が、という驚きも当時の私にはあったんですが、やはり硬い文脈も見えてくるんですよね。食の交感作用を充実させた暮らし、とでもいうのでしょうか。ここに少女性の話を加えると、ロハスガール、オーガニックコットンで身を包むような彼女たちも、出だしのころは、自分たちの美意識に閉じこもって牙城を打ち立てるように武装するという意味では、ゴスロリの少女たちと同じ意味をもっていたと思います。まず服飾に焦点を当てると、ゴスロリが黒くてけばけばしいレースだとか、もっといけば包帯を巻いたり眼帯をしだしたり、そういった服装になるのと一見反しているようですけれど、オーガニックコットンという自然有機的な素材で自分の身を守る、美意識を打ち立てるという意味では、あれも闘争のスタイルだったと思うんですよね。暮らしのなかでそれを脈々と営んでいく、ライフスタイルとして打ち立てていく先人として武田百合子を見出すということもできるのかも……深読みかもしれませんね。とにかく、私は美意識があまり合わないにせよ、「クウネル」の創刊号には「わお!」と目を見張った記憶があります。以後一切読んでいませんけれど。
ゴスロリ少女の打ち立て方より、あるいはロハスのほうの人たちのほうがラディカルなのでは、と思ったのはまさに食です。服装だけでなく、食にこだわるわけですから、内側から、いや、内蔵から変えていくわけですよね。外側を飾ることで武装したんじゃなくて内側に手を伸ばした、と読めばものすごい戦闘的な人たちかもしれない。……とはいえ、ロハスって消費に回収され気味だという感じがずっとあります。消費に回収されるどころか、放射性物質汚染に関して食が現実の大問題として浮上した今となっては、良くも悪くも、先鋭的ではない、現実応用可能なものになってしまったんですよね。だからというのか逆にというのか、いま注目するとしたらその現実応用性なんだろうと思います。
『きのう何食べた?』
著:よしながふみ
講談社
現実応用可能といえば料理本なんですけれど、みなさん料理はするんでしょうか。私はあまりしません。DOMMUNEで『味平』というプログラムをやっているんですが、必ずしもおいしさは追求していません。料理という行為には本質的に危なっかしいラディカルなものと、脈々としぶとくて普遍的な営みの、両方を感じています。
最近の料理本を見てみると、白い皿ばかりだなと感じます。あまり変哲のない、できるだけ装飾を排した白い皿やカップがおしゃれっぽい定番になっている気がするんですけど、あれって誤ったモダニズムの残骸な気もするんですよね。浸透しきっちゃった分、批判力は期待できないなぁとか。「カフェめし」って呼ばれる類いのゴハンがあるじゃないですか。ミニマムな皿できっちり腹八分目の一人前、スタミナ丼みたいな過剰さは決してない。「素材の味を活かしました」って謳われるけど、素材の味しかしなかったり。なんだか私は食欲がわかないんです、調教されてるような気分になったりもして。同じスカンピンならダイソーのほうが批判性を秘めてるよなぁ、と思います。普遍性というか浸透力という意味では白い皿もダイソーも今は並んでいると思うんですけど、白い皿が並ぶ家より、ダイソーで統一されてしまう家のほうに賭けたい気がしますね。ハングリーを歌った矢沢永吉がユニクロを着る世界です。
料理本を買おうと思ったんですけど、さて『きのう何食べた?』ですね。都内の2LDKに住まう弁護士と美容師の男性ふたりの日々の食事がつづられています。ふたりはゲイです。というとすぐに惚れた腫れたの恋愛ドラマやショッキングなセックスシーンや萌えを想像しますけど、セックスシーンなんて描かれません。セクシャルマイノリティだからといって期待しちゃダメです。日々温厚に淡々と重ねられる食事がふたりの愛の生活を描き出します。その点でBLと一線を画した作品ですよね。で、これはレシピ本にもなっています。無理なく素直に食卓の参考になるメニューばかりです。
同じよしながふみの作品でも『西洋骨董洋菓子店』は美形の男性たちが営むスイーツ店。女子がもつ甘味と美男子への萌えが同等に置かれていると思います。
あ、スイーツといえば、『木更津キャッツアイ』というドラマをご覧になっていましたか。恥ずかしながら私はガッツリ観てました。酒井若菜が演じているモー子という女子の素晴らしいシーンがあったんですよね。木更津というへんぴな土地に住むモー子は恋人役の櫻井翔に連れられて、渋谷原宿を連れ回されるんです。疲れてしまったモー子は宮下公園の歩道橋だったと思いますけれど、「クレープが食べたい」と座り込んでダダをこねるんです。それは「こんな街は嫌いだ」という意思表明なんです。ものがたくさん売ってて人もたくさんいて煌めいて眩しくて楽しそうだけど、彼女はなんにも楽しくない。いや、自分を見失いそうになる。そこで出た意思表明が「クレープが食べたい」。そして続けた二の句に私は胸が震えましたね。「クレープは私を裏切らないもん!」。これは自分を守るための、世界を手放さないための言葉なんですよ。モー子にとって世界の普遍はクレープによって捉えられているんです。木更津で食べようが、原宿で食べようが、パリで食べようが、ニューヨークで食べようが、モロッコで食べようが、病院で食べようが、刑務所で食べようが、クレープはクレープ、私を裏切らない。世界の普遍を信じるためのアイテムがモー子にとってはたまたまクレープだったというだけで、どこに見出すかは人それぞれにあるのだと思います。それにしてもモー子とクレープというのは最強の相性なんですよね。スイーツのやわなイメージも吹き飛ぶのではないでしょうか。女こどもが愛好する小さきものは卑小で低俗なものとみなされがちですけれども、はたしてどうでしょうね。
『ラデュレのお菓子レシピ』
著:フィリップ・アンドリュー
世界文化社
それで、スイーツのレシピなんです。この本自体がスイーツのようですね、というのを見越して作られたかのような装丁ですね。なんでこれを買ったかというと、スイーツを作りたかったわけではなく、スイーツの写真を眺めてみたいと思ったからです。刑務所に入っている男性たちが夢にまで見るのはスイーツなんだそうです。豪華な食事でも旅行でも女でもなく。出所後につきたい職業ベスト1がパーラー経営。スイーツをともにした身の振り方を夢見るそうなんですね。生体としての飢餓には塩や水が効くんだと思いますけど、精神的な飢えを解消するのはやっぱり甘味だと思うんですよね。
私には亡くなった父がいて、戦中戦後を体験している人間なんですけれど、戦後に世の中の人が白米をありがたがったという話をよく聞きますよね。薄茶色い麦飯が食えていただけでも御の字だったんですから、まして米の白さには目がつぶれるほど感動したというエピソードも耳にします。でも私の父は「米の白さに感動したって国中が言ったけど、そりゃウソだ」と言ってたんですよね。父がもっともショックだったのはマシュマロだったそうです。とにかく甘いものに飢えていたわけですが、それもさることながら「こんなに白い食べ物を見たことがなかった」という衝撃。たぶんそのときに父は、空腹だけではない、別の何かを満たすことを覚えたんだと思います。
『パリ直送レシピ!おうちで作れる本格マカロン』
著:ベランジェール・アブラハム
監修:奥田勝
世界文化社
雑誌にポーチだ鏡だノートだの付録がついてきてはむしろ付録のために雑誌を買っちゃうかもしれないというのが時流ですが、その本末転倒さが物理的な大きさにあらわれているのがこの製菓キット付きのレシピ本ですね。本格マカロンがつくれるそうです、ホイップクリーム絞り器がついてきます。余談ですけれど、先日まで並んでいた「ゼクシィ」には付録で婚姻届がついていましたね。何を考えているんでしょう。どんなに忙しくても役所くらい自分たちで行けばいいんじゃないかと思うんですけれども、これも「産めよ増やせよ」的な女子教育なのでしょうかと深読みしてしまいました。婚姻届も取りにいけないんだとしたら、女たちは忙しすぎですよ。
マカロンは好きです。でも高いですよね。高価だし流行りものだし、あれを箱買いするのは一種のステイタスだしパフォーマンスにもなりますけど。なんだかそこには別の欲望を感じるんですよね。私は2、3個買って帰るのが好きです。花泥棒とおなじ気持ちです。自分の好きなものを、自分が満たされるほんの少しだけ手に入れて帰るのが好きです。どら焼きなんかもね、基本は食べ歩くもので、箱買いするものじゃないと思ってます。ドラえもんはまた別です。
ほんとは人肉食の話も少ししようと思っていたんですよね。『ひかりごけ』じゃなくて『佐川君からの手紙』と『まんがサガワさん』。愛が高じて相手を食べてしまうっていうこととも、カニバリズムの祝祭とも、別のところにある気がして。これはまたあらためて。ちなみに私は死んだら食ってもらいたいなぁと思っていまして。別に死後のことは本人はわからないしどうでもいいんですけど、望むとしたらそういう弔い。でも強要はしません。時間も尽きたし遺言めいたし、というわけで、今夜はこれでさようなら。
「五所純子のド評」第六回目
2011年10月25日(火)
渋谷アップリンク・ファクトリー
気鋭の文筆家、五所純子が挑む90分モノローグ一本勝負の“書評のライブ・パフォーマンス”。毎月最終火曜日夜八時に開催。たいへん好評です。「前回とは全く違う風合いのものになったなあと終わってから気付く、即興演奏のようなド評です」(五所純子)
★今回は「娘たち」をテーマに書評が行われます。
19:30開場/20:00開演
出演:五所純子
料金:1,500円(1ドリンク付/予約できます)
※UPLINK会員は1,300円(1ドリンク付)
ご予約はこちらから