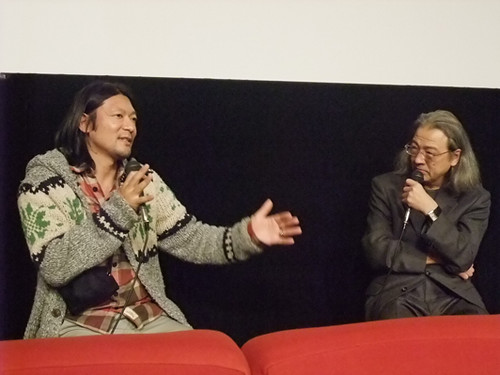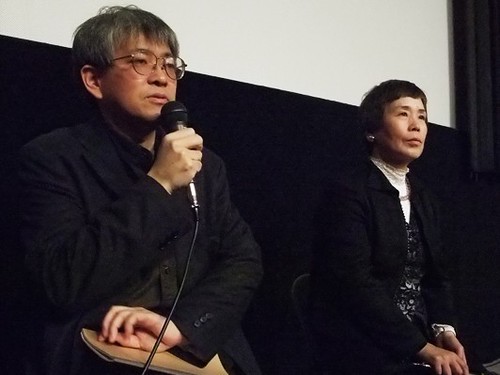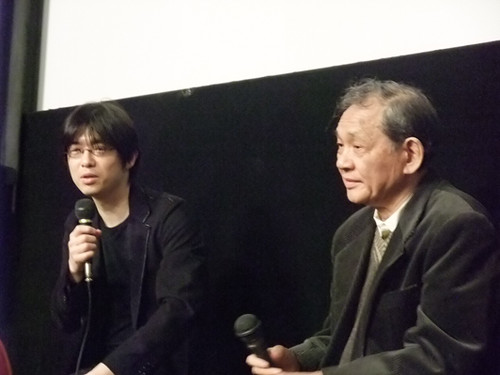渋谷シアター・イメージフォーラムにて映画『倫敦から来た男』公開記念スペシャルトークショーが全3回に渡って開催された。2009年12月17日は、写真家であり、自ら『星影のワルツ』『トーテム Song for home』など映画監督作も注目を集める若木信吾さんと、音楽や映画そして美術、舞台と広範なジャンルで活動を続けるプロデューサー/ディレクター立川直樹さんによる〈映像美を語る ~光と影の芸術作品~〉をテーマにしたトークが繰り広げられた。また12月19日は、映画評論家であり、映画監督としても『能楽師』『みやび 三島由紀夫』『なるしまフレンド 俺っち自転車道』などを手がける田中千世子さんと、映画プロデューサーとして、また東京フィルメックスのプログラム・ディレクターとしてそのスタートから精力的な活動を行う市山尚三さんが登壇。〈“監督タル・ベーラを語る”~世界の映画人を魅了する孤高の芸術家~〉という内容で貴重なエピソードが披露された。そして12月25日は、今作の原作小説の翻訳を手がけ、他にもジョルジュ・シムノン作品はもちろん数々のフランス文学を翻訳してきた長島良三さんと、2001年の『熊の敷石』芥川賞受賞をはじめとして数々の文学賞に輝く作家の堀江敏幸さんにより、〈“文豪ジョルジュ・シムノンを語る”~驚異のベストセラー作家、隠された素顔~〉と題して、文学の側面から対談が行われた。『ヴェルクマイスター・ハーモニー』(2000年)などの作品で熱狂的な支持を集めながら、日本の映画ファンにとっていまだベールに包まれたタル・ベーラ監督の素顔や『倫敦から来た男』の魅力を複合的に味わうことができる企画となった。
「これは〈訳のわかる芸術映画〉の最高峰」
若木信吾さん×立川直樹さん
12月17日のトークショーより、若木信吾さん(左)、立川直樹さん(右)
司会:「これほどの映画に出会えることは数えるほどしかない。」とまで仰った立川さん、この映画の見どころをおしえて頂けますか?
立川直樹(以下、立川):見どころはないんです。全部が見どころですから。全部がすごいんです。始まった瞬間から、このモノクロの光と影がコントロールされている。カメラの動き方などに見られるスピードも、俳優への演技のさせ方も素晴らしい。映画の中にある静かなバイブレーションを味わってほしいです。
若木信吾(以下、若木):僕は映画を観た後に原作小説を読みました。小説の冒頭に「人はその時の数時間を、いつもの数時間と同じように見なしてしまう。しかし、あとになってから、それが異例の数時間であったことに気づき、ひたすら失われたばらばらの数時間を復元しようと努め、脈絡のない一分一秒をつなぎ合わせようとする」とあるんです。まさにこの文から、タル・ベーラ監督がこの映画をつくろうとしたことが伝わってきました。
立川:今日、若木さんに訊いてみたいと思っていたのですが、実際に撮っている立場の人からすると、〈カラー〉と〈モノクロ〉はどのように違うのでしょう?
若木:カラーになる前のモノクロ映画というのは、モノクロしかないからモノクロで撮る、ということだったと思うんです。タル・ベーラ監督は意図的にモノクロを選んだことで、ものすごい黒の深いところや、 ものすごく明るいところを、モノクロででしかできない使い方で表現していますね。〈カラー〉があってこその〈モノクロ〉の良さが出ていると思います。
立川:この映画はものすごくシンプルでセリフも少ないですよね。「喋るわ、飛ぶわ」のハリウッド映画との境界線というのは何なのでしょうね?
若木:映像に対する信頼感、がすごくあるのではないでしょうか。
立川:あの波止場のシーンはセットだったことを知ってびっくりしたんです。映画には2種類あって、〈商業映画〉と〈芸術映画〉があると思います。さらに、〈訳のわからない芸術映画〉と〈訳のわかる芸術映画〉があって、この映画は〈訳のわかる芸術映画〉の最高峰だと思ったんです。あのセットの作り方にしても照明にしても。
若木:冒頭の船のシーンに対する集中力がものすごいので、そこが勝負なんです。集中力を使うのでゆっくり入っていったほうがいいです。
立川:そう、ふわぁーっと。最近、長廻しを意図的にする人は少ないと思うんです。僕は、ヴィスコンティ監督の『ベニスに死す』の冒頭を思い出しました。水平線に点が見えるのですが、「この点はなんだろう」と思っていて、ずっと近づいてくると船なんです。アンゲロプロス監督の『旅芸人の記録』の冒頭も思い出しました。そして、今回のこのタル・ベーラにも「やられたな」と思いました。
若木:一つの場所に対しての入り込ませ加減が、〈端折らない映画〉ですよね。
立川:〈端折らない〉というのはすごくいい表現ですね。商業映画では謎めいたものが無くなってきますから。ティルダ・スウィントンなどの女優もいいですね。
若木:ある雑誌で、堀江敏幸さんと対談した際にお話したのですが、ティルダ・スウィントンはフランス語が母語の人ではないから、少しクセのあるフランス語を話しているそうなんです。それがハンガリーのリアリティになっていて、とても良くて。
立川:ハンガリーに行った時に感じたのですが、〈モノクロ〉の感じなんです。ブダペストという街が持っているあの感じは、独特の哀しい感じがしますよね。
若木:僕にとっては、小さな国なのに全てが大きい、そのような感じがするんです。橋ですとか河の流れですとか。
立川:『倫敦から来た男』の冒頭の海のシーンがずっと続いているような感じですよね。
立川:写真と映画の一番大きな違いは何でしょう?
若木:映画には繋がりがあって、どんどんいいシーンが撮れるごとに、次のシーンがプレッシャーになっていくんです。「ここを逃してはいけない!」といったような。
立川:写真を撮っていると、映画も撮りたくなるものなのでしょうか?
若木:それは人それぞれだと思います。僕はその世界に入りたくなるんです。
立川:この映画が面白いのは、音楽にしてもあまり主張していませんね。すごいのは、ヨーロッパの人たちは職業を一つに決めていなくて自由ですよね。監督が映画に出たりとか脚本書いたりとか、他の所に行けば別のことをやっていたりして、自由さがありますよね。
若木:映画というものに対する愛情があっていいですよね。
「監督は歌舞伎と能が大好き」
市山尚三さん×田中千世子さん
12月19日に出演した市山尚三さん(左)、田中千世子さん(右)
司会:2003年に東京で行われたハンガリー映画祭で実行委員もされていましたお二人に監督タル・ベーラについて「世界の映画人を魅了する孤高の芸術家」というテーマでいろいろとお話して頂ければと思います。タル・ベーラ作品はジム・ジャームッシュやガス・ヴァン・サントなどの監督から絶賛されていますが、同じ映画監督である彼らが熱狂するのは、どのような部分だと思いますか?
田中千世子(以下、田中):私がタル・ベーラと初めて会ったのは25年ぐらい前です。その頃『秋の暦』(1985年)を観ました。ぴあフィルムフェスティバルが外国の新人監督を紹介してまして、上映もされました。ちょうど同じ時期にアメリカもインディーズ映画もブームで、それこそジャームッシュなども出てきた頃で、困難があっても製作をきちんとするという同じ境遇、同じ時代を共有しているからではないでしょうか。
市山尚三(以下、市山):『秋の暦』は今の作風とは全然違い、カラーでネオンサインみたいな作品です。お会いした時のタル・ベーラの印象はいかがでしたか?
田中:ほっそりとしたハンサムで、ブルーの目が印象的な虚弱そうな印象でした。今では“巨匠”という感じで怖いですが…。
市山:そうですね。どのような話をされたんですか?
田中:私のインタビューは尋問めいているのですが、どんな映画に影響をうけたの? などと質問攻めでした。
市山:影響を受けた映画はなんだとおしゃっていましたか?
田中:50年代のイギリス映画と言ってました。
市山:意外ですね。
田中:その他にもキング・ヴィダーの初期の作品のことを言ってました。“初期”というのを強調してました。
市山:僕が思うに、タル・ベーラの作品は最初の頃はジョン・カサベテスみたいな感じでセリフも多く、『秋の暦』もまた全然違う作風でしてカラーですし、『Damnation』(1987年)から今の作品のスタイルになってきましたね。
田中:『秋の暦』はハンガリーの社会主義の人からはけしからんと言われ、社会主義でない方にも嫌われて、行き場がなくなった時に『サタンタンゴ』(1994年)の原作者と出会ったんですが、今のハンガリーでは撮れないので、規模を小さくした感じで『Damnation』を撮影したんだと思います。
市山:『秋の暦』の時は日本に来てますよね? その頃の日本での反応はいかがでした?
田中:意地の悪い評論家の方は「(イングマール・)ベルイマンを真似している!」っておしゃってましたよ。
市山:ベルイマン!? 家族の崩壊というところですかね?僕は(ライナー・ヴェルナー・)ファスビンダーに似ているかと思いました。
田中:本人は日本が好きで、歌舞伎と能を観にいってました。来る前に勉強していたみたいです。
市山:東京国際映画祭で『サタンタンゴ』の上映をする時に、能楽堂でゲストが能を鑑賞するというのがありまして、興味がない人も多かったのですが、公式行事なので参加するように促したりしていました。タル・ベーラは来た時から「いつ観れるんだ」「どこで観れるんだ」と、すごくやる気満々だったんです。ところが、その時に観たのが想像していたのと違っていたらしく、「西洋の悪影響をうけている」と怒り狂ってたらしいです。
田中:それと「東京の猫の尻尾が短い」と怒っていたらしいですよ。日本人は猫の尻尾を切ってるのか!!って(笑)。
市山:その時の東京国際映画祭での『サタンタンゴ』上映は平日の昼間に行ったんですね。7時間30分あるので、申し訳ないですが、他の上映作品との兼ね合いもあり、平日しかできなかったんです。それでも400人近い人が観に来てくれて「すごいな!」と喜んでいたら「なぜ満席じゃないんだ。東京にはこんなにも人がいるのになぜ来ない!」と怒っていましたね。「これでもすごい入っている」とは一応伝えましたが。
司会:新作について教えて下さい。
市山:現在、新作を撮影中です。ニーチェがトリノに行った時に虐待されている馬を助けようとして発狂する『トリノの馬』のエピソードから、発想を得た作品だそうです。馬を飼っている親子の話で、『倫敦から来た男』の主演のミロスラヴ・クロボットと娘役のポーク・エリカがまた親子役で共演しているそうです。ハンガリーの田舎で撮影しているようで、またハンガリー独特のドロっとした映像が観れるはずではと期待しています。
「『倫敦から来た男』は犯罪小説というより心理小説」
堀江敏幸さん×長島良三さん
イベント第3弾に登壇した堀江敏幸さん(左)、長島良三さん(右)
司会:最初にこの映画をご覧になられてのご感想は?
長島良三(以下、長島):この監督は、シムノンの作品をよく読んでいると思います。シムノンは若い頃から海が好きで、波止場を舞台にした作品がたくさんあります。この映画は最初、波止場のシーンから始まっていて、延々と撮っていますよね。そういうところを観ると、ああ、監督はシムノンをよく知っているな、と思いました。
堀江敏幸(以下、堀江):おびただしい数の作品がある中で、これは既に2回映画化されています。原作に、すごく惹かれるところがあったのではないでしょうか。映画の手触りとは別に、もっと深い文学的な理解がある作品だと思います。
堀江:僕は年下で、今日はあえて〈長島さん〉と呼ばせて頂いておりますが、僕からすると〈長島先生〉とお呼びするくらい、長島さんの翻訳で育ったんです。シムノンは、「メグレ警視」シリーズとは別に〈本格小説〉という流れの作品を書いていて、『倫敦から来た男』は1930年代に書かれたものです。長島さんに質問ですが、シムノンは何故「メグレ警視」シリーズと違う路線を書こうとしたのでしょうか?
長島:コナン・ドイルもそうですけれど、シムノンも最初は作家を目指していたわけです。ところが、たまたま「メグレ」を書いて有名になってしまい、「メグレ」の注文ばかりが来るようになります。彼としては、「自分はちゃんとした小説が書けるんだ、「メグレ」だけではないんだ」という思いを抱いていたわけなんです。段々と自分の書きたいものを書けるようになっていったと思います。
堀江:シムノンはもともとはベルギーから出てきたんですよね?
長島:はい、ベルギーのリエージュです。
堀江:ベルギーでもフランス語が母国語ですが、彼がフランスに来たときは、やはり少し訛りのようなものがあったのでしょうか?
長島:彼は二十歳のときに奥さんとパリに出てきたわけですが、自叙伝には言葉の問題についてはあまり書いていないですね。だから、あまりそういうことではいじめられなかったと思うんです。ただ、仕事はなくて、絵描きの奥さんがモンマルトルのテアトル広場で、観光客を相手に似顔絵を描いていました。シムノンは、そのそばの喫茶店でタイプライターを借りて作品を書いていました。その頃の貧乏な暮らしについては書いていますよ。
堀江:長島さんの翻訳でも見事に表されていますが、シムノンのフランス語はとても美しいですね。
長島:彼が若い頃、コレットが雑誌の編集者をしていた時に、原稿を持ち込んで、よく見てもらっていたんです。コレットに、文章をだいぶん削られていたらしいんです。そして、段々と簡潔な文になっていったようです。
堀江:コレットは、わりに姉御肌の人で、若い頃のシムノンの小説を読んで「過度に文学的なところを削れ」とアドバイスをしていたんですよね。そういうことがあって、シムノンが1930年代に書いた作品は、日本的に言うと、いわゆる純文学の世界の書き方と言えます。日本ではあまり読まれませんが、アンドレ・ジッドもシムノンにお墨付きを与えています。タル・ベーラが選んだこの『倫敦から来た男』は1934年の作品で、英仏海峡が舞台ですが、この作品に至る前に、シムノンはロシア文学をよく読んでいたんですよね?
長島:はい。ベルギーには、ロシアから留学生、特に医学生がたくさん来ていて、シムノンのお母さんは、家の2Fをロシア人留学生に貸していたんです。それで、シムノンは彼等と色々話していてロシア文学を知ったんです。ですから、ロシア文学に詳しいんです。特にドストエフスキーから影響を受けたと思います。
堀江:まさにドストエフスキーは、『倫敦から来た男』の前のタル・ベーラの映画にも大きな影を与えていると、僕は個人的には思います。モノクロの映画で、光と闇があり、リズムだけでない無限の諧調(かいちょう)があります。『倫敦から来た男』は、「犯罪小説」の形態をとってはいますが、むしろ「心理小説」ですよね。これはフランスの伝統なのでしょうか?
長島:これは、サスペンスの犯罪小説といったほうがいいんじゃないでしょうか。この作品の頃は、まだ出版社には「メグレ警視」シリーズしか書かせてもらえない、そういった状況の中で書いていたんです。
堀江:すごく人を惹きつける書き方をしていながら、通俗にはならない。犯罪やサンスペンスがあるのですが、最終的には犯罪がどうだのとか犯人がどうだのということではなくて、主人公だけでなく登場人物全員にシムノンの目が行き届いているんです。
長島:シムノンがこの原稿を編集者に渡したときに、「これはカミュに近いんじゃないか」と言われたんです。
堀江:「異邦人」のカミュはフランス文学のエースでしたね。シムノンの「メグレ」でない小説が出てきた時に、カミュと比較されたんです。ある種の〈不条理〉、つまり人間がある闇に向かっていくというような部分で。
長島:シムノン作品には、最初からそうでしたけれど、平々凡々な生活を送るごく普通の人間が、そして大部分が下層階級にいる人間が、ある日意外な事件に遭遇したり、あるいは、目撃したりして、その人の生活が一変してしまう、そういうところがあるんです。シムノン自身は自分の小説のことを〈運命の小説〉と呼んでいます。この『倫敦から来た男』では、北フランスのディエップの港湾駅の転轍士が、奥さんと子どもと幸せに平凡な生活を送っていたのに、ある日事件を目撃してしまう…。そのために人生が一変して追い詰められてしまう……。シムノンは、ある局面に人間を放り込んで、その人がどのように生きてゆくかを書いています。それが自分の使命だと言っています。
堀江:シムノンの小説を読んでいると、最初から、普通の人の中にも闇の部分があるんだということがわかりますね。そして、そういったことを、説明したりするのではなくて映画のように場面転換でみせてゆきます。原作の『倫敦から来た男』は、訳されていて、何かご苦労などはありましたか?
長島:一番苦労したのは、映画の公開に間に合わせなければならなかったことです(笑)。翻訳で非常に苦労するのは、シムノンは簡潔に書いているので、そのまま訳すと日本語として通じない部分があるんです。どしても、”付け足し”をしなくてはならない、でもあまりやり過ぎてもだらだらした文章になったりしますし、どこまでやるかが難しいんです。
堀江:それは本当にベテランの仕事ですね。過去に起きた物事のことも、今まさに起こっているように訳さなくてはならなかったりするんですよね。物事の順序をそのまま書かれている通りに訳してしまうと、分からなくなってしまうので、少し時制を入れかえないと流れが悪くなってしまったりしてしまいますが、ここが(長島さんの翻訳では)見事に処理されています。映画をご覧になった後に原作を読まれると、多少異なる部分も含めて、二倍楽しめると思います。
『倫敦から来た男』
シアター・イメージフォーラム他、全国ロードショー公開中
監督:タル・ベーラ
原作:ジョルジュ・シムノン「倫敦(ロンドン)から来た男」(河出書房新社)
共同監督・編集:フラニツキー・アーグネシュ
出演:ミロスラヴ・クロボット、ティルダ・スウィントン
2007年/ハンガリー=ドイツ=フランス/138分/35mm/ヨーロピアンビスタ/ドルビーデジタル
後援:駐日ハンガリー共和国大使館、ハンガリー政府観光局
配給:ビターズ・エンド
公式サイト